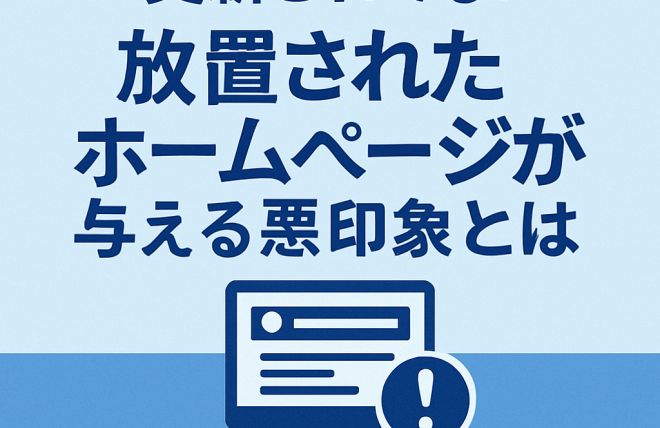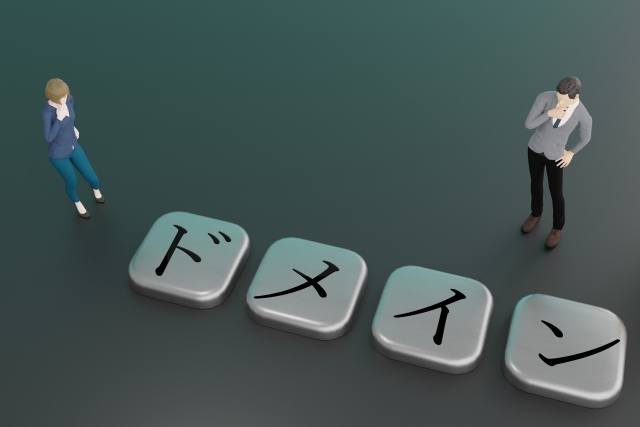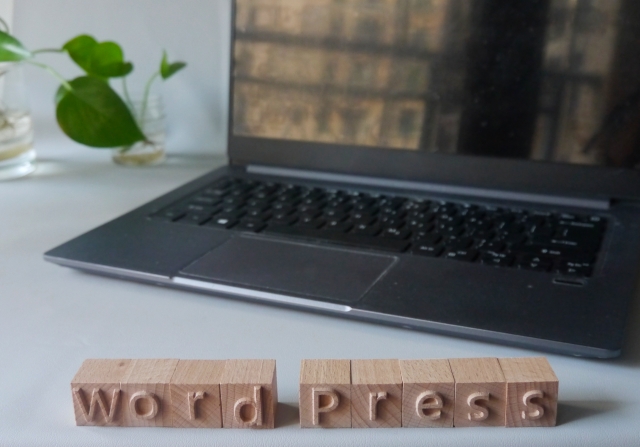гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®еҸҚеҝңгҒҢжӮӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгӮүгҖҒе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгӮ’иҰӢзӣҙгҒҷгғҒгғЈгғігӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣж•°гӮ’гӮўгғғгғ—гҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«иЁӯзҪ®гҒҷгҒ№гҒҚ5гҒӨгҒ®е°Һз·ҡгғқгӮӨгғігғҲгӮ’и§ЈиӘ¬гҖӮеҠ№жһңзҡ„гҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ§CVгӮ’жңҖеӨ§еҢ–гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гҒЁгҒҜпјҹ
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҜгҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғігӮ’жңҖеӨ§еҢ–гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«ж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„иҰҒзҙ гҒ§гҒҷгҖӮгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«зӣ®зҡ„гғҡгғјгӮёгҒёиҫҝгӮҠзқҖгҒ‘гӮӢиЁӯиЁҲгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒжғ…е ұгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҡгҒ«йӣўи„ұгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ„иіје…ҘгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮҙгғјгғ«гӮ’йҒ”жҲҗгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҢеҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒҰйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгӮ’йҒ©еҲҮгҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјдҪ“йЁ“гҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҖҒзөҗжһңзҡ„гҒ«жҲҗжһңгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢеҠ№жһңгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е°Һз·ҡгҒЁеӢ•з·ҡгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢ
гҖҖгҒҫгҒҡгҖҒе°Һз·ҡгҒЁеӢ•з·ҡгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’жҳҺзўәгҒ«зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢе°Һз·ҡгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеҲ¶дҪңиҖ…гҒҢж„Ҹеӣізҡ„гҒ«иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгӮ’зӣ®зҡ„ең°гҒ«иӘҳе°ҺгҒҷгӮӢзөҢи·ҜгӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒгҖҢеӢ•з·ҡгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢиҫҝгҒЈгҒҹиЎҢеӢ•зөҢи·ҜгӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®дәҢгҒӨгҒҜдјјгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЁӯиЁҲж®өйҡҺгҒ§ж„ҸиӯҳгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгғқгӮӨгғігғҲгҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒе°Һз·ҡгҒҜдәӢеүҚгҒ«иЁҲз”»гҒ—гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢзӣҙж„ҹзҡ„гҒ«ж“ҚдҪңгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зӣ®зҡ„гғҡгғјгӮёгҒёе°ҺгҒҸеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒеӢ•з·ҡгҒҜеҲҶжһҗеҜҫиұЎгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ©гҒ®гғҡгғјгӮёгӮ’зөҢз”ұгҒ—гҒҰзӣ®зҡ„ең°гҒ«гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиЁӯиЁҲгҒ®гҒ©гҒ“гҒ«ж”№е–„гғқгӮӨгғігғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҒҢжҳҺзўәгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҢгӮӮгҒҹгӮүгҒҷеҠ№жһңгҒЁгҒҜ
гҖҖйҒ©еҲҮгҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғ“гғӘгғҶгӮЈгҒ®еҗ‘дёҠгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёе…ЁдҪ“гҒ®жҲҗжһңгҒ«зӣҙзөҗгҒҷгӮӢеҠ№жһңгӮ’зҷәжҸ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢзӣ®зҡ„гҒ®жғ…е ұгҒёгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гҒӘгҒҸгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢз’°еўғгӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгҒҢиҮӘ然гҒЁдёҠжҳҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҢеў—гҒҲгӮӢпјҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«иЁӯзҪ®гҒҷгҒ№гҒҚ5гҒӨгҒ®е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒЁгҒҜпјҹгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе…·дҪ“зҡ„гҒӘж–Ҫзӯ–гӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣж•°гҒ®еў—еҠ гӮ„е•Ҷе“Ғиіје…ҘзҺҮгҒ®еҗ‘дёҠгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘжҲҗжһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢиҝ·гӮҸгҒӘгҒ„иЁӯиЁҲгҒҜгӮөгӮӨгғҲгҒёгҒ®дҝЎй јж„ҹгӮ’й«ҳгӮҒгҖҒеҶҚиЁӘе•ҸгӮ„еҸЈгӮігғҹгӮ’з”ҹгӮҖгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гӮ’дҪңгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҢдёҚеҚҒеҲҶгҒӘе ҙеҗҲгҖҒйӣўи„ұзҺҮгӮ„зӣҙеё°зҺҮгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжҲҗжһңгҒ®дҪҺдёӢгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮй•·жңҹзҡ„гҒ«иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒйӣҶе®ўгӮ„еҸҺзӣҠгҒ«гӮӮеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒҷгҒҹгӮҒгҖҒгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁиЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гҒЁе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ®й–ўдҝӮ
гҖҖе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҒҹдёҠгҒ§иЁҲз”»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮгӮҝгғјгӮІгғғгғҲгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӢ•ж©ҹгҒ§гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’иЁӘгӮҢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жғ…е ұгӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҲқгӮҒгҒҰеҠ№жһңзҡ„гҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢеҲқеҝғиҖ…гҒ«гӮӮгӮҸгҒӢгӮӢж”№е–„гғқгӮӨгғігғҲи§ЈиӘ¬гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҲҮгӮҠеҸЈгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҖҒеҲқеҝғиҖ…гҒҢжұӮгӮҒгӮӢжғ…е ұгҒёгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйӣўи„ұзҺҮгӮ’дёӢгҒ’гӮӢеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгҒ©гҒ®гғҡгғјгӮёгҒ§жңҖгӮӮй•·гҒҸж»һеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒ©гҒ®гғҡгғјгӮёгҒӢгӮүгӮөгӮӨгғҲгӮ’йӣўгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеӢ•еҗ‘гӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘжғ…е ұгӮ„CTAпјҲгӮігғјгғ«гғ»гғҲгӮҘгғ»гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғіпјүгӮ’зӣ®з«ӢгҒӨдҪҚзҪ®гҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гҒЁе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҜеҜҶжҺҘгҒ«й–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘеҲҶжһҗгҒЁж”№е–„гҒҢжҲҗжһңгӮ’дёҠгҒ’гӮӢйҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ®еҹәжң¬
гғҰгғјгӮ¶гғјдҪ“йЁ“гӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҹиЁӯиЁҲгҒ®гғқгӮӨгғігғҲ
гҖҖ гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғігӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјдҪ“йЁ“гӮ’жңҖе„Әе…ҲгҒ«иҖғгҒҲгҒҹе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢзӣҙж„ҹзҡ„гҒ«зӣ®зҡ„гҒ®жғ…е ұгҒ«гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгғҠгғ“гӮІгғјгӮ·гғ§гғіиЁӯиЁҲгӮ„гҖҒгғҡгғјгӮёж§ӢжҲҗгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғ•гӮ©гғјгғ гӮ„иіје…ҘгғҡгғјгӮёгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮҙгғјгғ«ең°зӮ№гҒҫгҒ§гҒ®йҒ“зӯӢгҒҢгӮ·гғігғ—гғ«гҒ§еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҲқеҝғиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйӣўи„ұзҺҮгӮ’дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгҖҒжҺҘи§Ұй »еәҰгӮ’еў—гӮ„гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ гҒҫгҒҹгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®зӣ®з·ҡгӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮиҰ–иҰҡзҡ„гҒ«жҳҺзўәгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ„гҖҒйҒ©еҲҮгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гӮ’ж„ҹгҒҳгҒӘгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёе…ЁдҪ“гҒ®еҚ°иұЎгҒҢиүҜгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеҶҚиЁӘе•ҸгӮ„е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣж•°гҒҢеў—гҒҲгӮӢеҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҢеў—гҒҲгӮӢпјҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«иЁӯзҪ®гҒҷгҒ№гҒҚ5гҒӨгҒ®е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғҶгғјгғһгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҖҒиҮӘзӨҫгӮөгӮӨгғҲгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘиҰҒзҙ гӮ’жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ®гӮ№гғҶгғғгғ—пјҡгӮҙгғјгғ«иЁӯе®ҡгҒӢгӮүеӢ•з·ҡиЁӯиЁҲгҒҫгҒ§
гҖҖ еҠ№жһңзҡ„гҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ®з¬¬дёҖжӯ©гҒҜгҖҒзӣ®зҡ„гҒЁгӮҙгғјгғ«гӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ«жңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒ©гҒ®гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғігӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘжҲҗжһңгӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮе•Ҷе“Ғиіје…ҘгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒёгҒ®еҘ‘зҙ„гҖҒиіҮж–ҷгҒ®гғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮҙгғјгғ«гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰиЁӯиЁҲгӮ’йҖІгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ ж¬ЎгҒ«гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјиҰ–зӮ№гҒ§гҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№зөҢи·ҜгӮ’ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҡгғјгӮёж§ӢжҲҗгӮ„гғӘгғігӮҜгӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮҢгҒ°гӮ№гғ гғјгӮәгҒӘе°Һз·ҡгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮ’иЁҲз”»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж®өйҡҺгҒ§гҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢе®ҹйҡӣгҒ«гҒҹгҒ©гӮӢеӢ•з·ҡгӮӮжҠҠжҸЎгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҲгғғгғ—гғҡгғјгӮёгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®гғҡгғјгӮёгҒҢгӮ·гғјгғ гғ¬гӮ№гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиЁӯиЁҲгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ гӮҙгғјгғ«иЁӯе®ҡгҒӢгӮүеӢ•з·ҡиЁӯиЁҲгҒҫгҒ§гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—зўәиӘҚгҒ—гҖҒдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйғЁеҲҶгӮ’иЈңгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҠ№жһңзҡ„гҒӘе°Һз·ҡгӮ’е®ҢжҲҗгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҜгҖҒзөҗжһңзҡ„гҒ«гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢеӨ§гҒҚгҒӘгӮ«гӮ®гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҠ№жһңзҡ„гҒӘCTAпјҲгӮігғјгғ«гғ»гғҲгӮҘгғ»гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғіпјүгҒ®жҙ»з”Ё
гҖҖ CTAпјҲгӮігғјгғ«гғ»гғҲгӮҘгғ»гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғіпјүгҒЁгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ«зү№е®ҡгҒ®гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғігӮ’дҝғгҒҷиҰҒзҙ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ®жҲҗеҠҹгҒ«ж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„иҰҒзҙ гҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢд»ҠгҒҷгҒҗгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҷгӮӢгҖҚгӮ„гҖҢз„Ўж–ҷзҷ»йҢІгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғңгӮҝгғігӮ„гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ«и©ІеҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®еҗ„жүҖгҒ«йҒ©еҲҮгҒӘCTAгӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢж¬ЎгҒ«еҸ–гӮӢгҒ№гҒҚиЎҢеӢ•гӮ’жҳҺзўәгҒ«зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ еҠ№жһңзҡ„гҒӘCTAгӮ’иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒиҰ–иӘҚжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸзӣ®з«ӢгҒӨгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйӯ…еҠӣзҡ„гҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢиЁҖи‘үгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒCTAгӮ’й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢе ҙжүҖгӮӮжҲҗеҠҹгӮ’е·ҰеҸігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғҲгғғгғ—гғҡгғјгӮёгӮ„е•Ҷе“Ғи©ізҙ°гғҡгғјгӮёгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢиЎҢеӢ•гӮ’е®ҢдәҶгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гӮҙгғјгғ«зӣҙеүҚгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҜгғӘгғғгӮҜзҺҮгҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ гҒ•гӮүгҒ«гҖҒCTAгҒ®еҠ№жһңгӮ’жӨңиЁјгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиӨҮж•°гҒ®гғҗгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігҒ§A/BгғҶгӮ№гғҲгӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’иёҸгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®еҸҚеҝңгҒҢиүҜгҒ„е°Һз·ҡгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ„гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғіж•°гҒ®еў—еҠ гҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғўгғҗгӮӨгғ«гғ•гғ¬гғігғүгғӘгғјгҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲ
гҖҖ иҝ‘е№ҙгҖҒгғўгғҗгӮӨгғ«з«Ҝжң«гҒӢгӮүгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгғўгғҗгӮӨгғ«гғ•гғ¬гғігғүгғӘгғјгҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮ№гғһгғјгғҲгғ•гӮ©гғігӮ„гӮҝгғ–гғ¬гғғгғҲгҒ§гҒ®й–ІиҰ§жҷӮгҒ«гӮӮгҖҒгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гҒӘгҒҸж“ҚдҪңгҒ§гҒҚгӮӢгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйӣўи„ұзҺҮгӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«дҪҺжёӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖ е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғңгӮҝгғігӮ„гғӘгғігӮҜгӮ’еҚҒеҲҶгҒӘеӨ§гҒҚгҒ•гҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҖҒгӮҝгғғгғҒж“ҚдҪңгҒ§гӮӮгӮ№гғ гғјгӮәгҒӘеӢ•гҒҚгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҡгғјгӮёгҒ®иӘӯгҒҝиҫјгҒҝйҖҹеәҰгӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгғўгғҗгӮӨгғ«гғҰгғјгӮ¶гғјгҒҜиЎЁзӨәгҒҢйҒ…гҒ„гҒЁгҒҷгҒҗгҒ«йӣўи„ұгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒи»ҪйҮҸеҢ–гҒ—гҒҹгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’еҝғгҒҢгҒ‘гӮӢгҒЁиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҖ гҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғ¬гӮ№гғқгғігӮ·гғ–гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒ«еҝңгҒҳгҒҹжңҖйҒ©гҒӘиЎЁзӨәгӮ’е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгғўгғҗгӮӨгғ«гғ•гғ¬гғігғүгғӘгғјгҒӘиЁӯиЁҲгҒҜгҖҒSEOеҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёе…ЁдҪ“гҒ®йӣҶе®ўеҠӣгӮ’й«ҳгӮҒгҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮдёҠжҳҮгҒёгҒ®иІўзҢ®гҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
жҲҗеҠҹдәӢдҫӢгҒӢгӮүеӯҰгҒ¶е°Һз·ҡиЁӯиЁҲ
гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғігҒҢеӨ§е№…гҒ«дёҠгҒҢгҒЈгҒҹдәӢдҫӢ
гҖҖгҒӮгӮӢдјҒжҘӯгҒ§гҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гғӘгғӢгғҘгғјгӮўгғ«жҷӮгҒ«е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгӮ’иҰӢзӣҙгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣж•°гҒҢйЈӣиәҚзҡ„гҒ«еў—еҠ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢжұӮгӮҒгӮӢжғ…е ұгҒ«зӣҙж„ҹзҡ„гҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒжңҖйҒ©гҒӘгғҠгғ“гӮІгғјгӮ·гғ§гғігӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҠ№жһңзҡ„гҒӘCTAпјҲгӮігғјгғ«гғ»гғҲгӮҘгғ»гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғіпјүгғңгӮҝгғігӮ’йҮҚиҰҒгҒӘз®ҮжүҖгҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®иЎҢеӢ•гӮ’дҝғйҖІгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒзӣҙеё°зҺҮгҒҢ30%дҪҺдёӢгҒ—гҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгҒҢ40%еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҲҗжһңгӮ’дёҠгҒ’гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®еӢ•гҒҚгӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒ—гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёе…ЁдҪ“гҒ®еҠ№жһңгӮ’еӨ§е№…гҒ«еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ«еӨұж•—гҒ—гҒҹдҫӢгҒЁгҒқгҒ®ж•ҷиЁ“
гҖҖдёҖж–№гҒ§гҖҒе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҢдёҚеҚҒеҲҶгҒ гҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ«жҲҗжһңгӮ’дёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеҲҘгҒ®дјҒжҘӯгҒ§гҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гӮҙгғјгғ«гҒҢжҳҺзўәгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’е„Әе…ҲгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢзӣ®зҡ„гҒ®жғ…е ұгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҡгҒ«йӣўи„ұгҒҷгӮӢдәӢж…ӢгҒҢй »зҷәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғ•гӮ©гғјгғ гҒҢж·ұгҒ„йҡҺеұӨгҒ«йҡ гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҖҒиӮқеҝғгҒ®CTAгғңгӮҝгғігҒҢзҙӣгӮүгӮҸгҒ—гҒ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгҒҢдҪҺиҝ·гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӨұж•—гҒӢгӮүеҫ—гӮүгӮҢгӮӢж•ҷиЁ“гҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒҜиҰӢж „гҒҲгҒ®иүҜгҒ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®еӢ•гҒҚгӮ’еҝөй ӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе°Һз·ҡгӮ’иЁҲз”»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
еҗ„жҘӯз•ҢгҒ§гҒ®еҠ№жһңзҡ„гҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲдҫӢ
гҖҖе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҜжҘӯз•ҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҮҚзӮ№гӮ’зҪ®гҒҸгғқгӮӨгғігғҲгҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒECгӮөгӮӨгғҲгҒ§гҒҜе•Ҷе“ҒгҒ®жӨңзҙўжҖ§гӮ„иіје…ҘгҒҫгҒ§гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’гӮ·гғігғ—гғ«гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒӮгӮӢеӨ§жүӢECгӮөгӮӨгғҲгҒ§гҒҜгҖҒе•Ҷе“ҒжӨңзҙўгҒӢгӮүгӮ«гғјгғҲжҠ•е…ҘгҖҒжұәжёҲгҒҫгҒ§гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’3гӮҜгғӘгғғгӮҜд»ҘеҶ…гҒ§е®ҢзөҗгҒ•гҒӣгӮӢиЁӯиЁҲгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеЈІдёҠгҒҢ2еҖҚгҒ«еў—еҠ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҖж–№гҖҒBtoBгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гҒҜгҖҒиіҮж–ҷи«ӢжұӮгӮ„е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒ®е°Һз·ҡгӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮжҲҗеҠҹдәӢдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒFAQгғҡгғјгӮёгҒ®гғӘгғігӮҜгӮ’зӣ®з«ӢгҒҹгҒӣгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣж•°гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҹгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжҘӯз•ҢгӮ„гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒҢгҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғігӮ’й«ҳгӮҒгӮӢеҠ№жһңзҡ„гҒӘжүӢж®өгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҲҶжһҗгҒЁж–Ҫзӯ–
е°Һз·ҡеҲҶжһҗгҒ®жүӢжі•гҒЁгғ„гғјгғ«
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§жҲҗжһңгӮ’дёҠгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒ®йҒ©еҲҮгҒӘеҲҶжһҗгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҲҶжһҗгҒ®з¬¬дёҖжӯ©гҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮөгӮӨгғҲеҶ…гӮ’移еӢ•гҒ—гҖҒгҒ©гҒ®зөҢи·ҜгҒ§зӣ®зҡ„гҒ®жғ…е ұгӮ„зӣ®жЁҷгҒ«гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жғ…е ұгӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дјҒжҘӯгҒҜGoogle AnalyticsгҒӘгҒ©гҒ®гғ„гғјгғ«гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖGoogle AnalyticsгҒ§гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гғҡгғјгӮёгҒҢжңҖгӮӮеӨҡгҒҸй–ІиҰ§гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒзӣҙеё°зҺҮгҒҢй«ҳгҒ„гғҡгғјгӮёгҒҜгҒ©гҒ“гҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгҒ©гҒ®гғҡгғјгӮёгҒ§гӮөгӮӨгғҲгӮ’йӣўи„ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғҮгғјгӮҝгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢиЎҢеӢ•гғ•гғӯгғјгҖҚж©ҹиғҪгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢе®ҹйҡӣгҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘй ҶеәҸгҒ§гғҡгғјгӮёгӮ’移еӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе°Һз·ҡгҒ®ж”№е–„гҒ«еҪ№з«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гғ„гғјгғ«гҒ®еҲ©з”ЁгӮӮжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮзҶұгҒҢйӣҶдёӯгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйғЁеҲҶгҒҜгӮҜгғӘгғғгӮҜгӮ„й–ўеҝғгҒҢй«ҳгҒ„гӮЁгғӘгӮўгӮ’зӨәгҒ—гҖҒйҖҶгҒ«еҶ·гҒҹгҒ„йғЁеҲҶгҒҜгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢдёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮЁгғӘгӮўгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҜгҖҒгғ’гғјгғӯгғјгӮӨгғЎгғјгӮёгӮ„CTAsпјҲгӮігғјгғ«гғ»гғҲгӮҘгғ»гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғіпјүгҒ®й…ҚзҪ®ж”№е–„гҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҮгғјгӮҝгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹе°Һз·ҡж”№е–„гҒ®гӮўгӮӨгғҮгӮў
гҖҖеҲҶжһҗгғҮгғјгӮҝгӮ’е…ғгҒ«ж”№е–„жЎҲгӮ’иҖғгҒҲгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒ®иЎҢеӢ•гғ‘гӮҝгғјгғігҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҖҒзӣ®зҡ„гҒ«жІҝгҒЈгҒҹе°Һз·ҡгҒ®жңҖйҒ©еҢ–гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣж•°гӮ’еў—гӮ„гҒ—гҒҹгҒ„е ҙеҗҲгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгғ•гӮ©гғјгғ гҒёгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№е°Һз·ҡгӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғҲгғғгғ—гғҡгғјгӮёгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гғҡгғјгӮёгҒ«зӣ®з«ӢгҒӨCTAгғңгӮҝгғігӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒзӣҙеё°зҺҮгҒҢй«ҳгҒ„гғҡгғјгӮёгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжғ…е ұдёҚи¶ігҒҢеҺҹеӣ гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«еҝңгҒҳгҒҹиҝҪеҠ гӮігғігғҶгғігғ„гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеҶ…йғЁгғӘгғігӮҜгӮ’еў—еҠ гҒ•гҒӣгҒҰд»–гҒ®й–ўйҖЈжғ…е ұгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§ж”№е–„гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгҖҢгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҢеў—гҒҲгӮӢпјҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«иЁӯзҪ®гҒҷгҒ№гҒҚ5гҒӨгҒ®е°Һз·ҡиЁӯиЁҲгҒЁгҒҜпјҹгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮігғігғҶгғігғ„гӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®зӣ®гӮ’еј•гҒҚгҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғігҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғўгғҗгӮӨгғ«гғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®еў—еҠ гҒ«дјҙгҒ„гҖҒеӢ•з·ҡгҒ®иЁӯиЁҲгҒҢгғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒ«жңҖйҒ©еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгӮҝгғғгғ—гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гғңгӮҝгғігӮөгӮӨгӮәгӮ„гғ¬гӮ№гғқгғігӮ·гғ–гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®дҪҝгҒ„еӢқжүӢгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
A/BгғҶгӮ№гғҲгҒ§е°Һз·ҡгҒ®жңүеҠ№жҖ§гӮ’жӨңиЁј
гҖҖж”№е–„зӯ–гҒҢе…·дҪ“еҢ–гҒ—гҒҹгӮүгҖҒA/BгғҶгӮ№гғҲгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒқгҒ®еҠ№жһңгӮ’жӨңиЁјгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮA/BгғҶгӮ№гғҲгҒЁгҒҜгҖҒз•°гҒӘгӮӢгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ„иҰҒзҙ гӮ’жҜ”ијғгҒ—гҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒҢгӮҲгӮҠиүҜгҒ„зөҗжһңгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгғҶгӮ№гғҲжүӢжі•гҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғҲгғғгғ—гғҡгғјгӮёгҒ®CTAгғңгӮҝгғігҒ®иүІгӮ’еӨүгҒҲгҒҹгӮҠгҖҒй…ҚзҪ®е ҙжүҖгӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®еҸҚеҝңгӮ’жҜ”ијғгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖA/BгғҶгӮ№гғҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе°Һз·ҡеӨүжӣҙеүҚеҫҢгҒ®зӣҙеё°зҺҮгӮ„гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгҖҒгӮЁгғігӮІгғјгӮёгғЎгғігғҲзҺҮгҒӘгҒ©гҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒгҒ©гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ„й…ҚзҪ®гҒҢгғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гҒ«гӮҲгӮҠгғқгӮёгғҶгӮЈгғ–гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒӢгӮ’еҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҖҢеҲқеҝғиҖ…гҒ«гӮӮгӮҸгҒӢгӮӢж”№е–„гғқгӮӨгғігғҲи§ЈиӘ¬гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе®ҹйҡӣгҒ«еҠ№жһңгҒ®гҒӮгӮӢж–Ҫзӯ–гӮ’е°ҺгҒҚеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖйҒ©еҲҮгҒӘе°Һз·ҡиЁӯиЁҲгӮ’зўәз«ӢгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҮгғјгӮҝгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹжӨңиЁјгҒЁз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘж”№е–„гҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгғҮгғјгӮҝгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјзӣ®з·ҡгҒ§гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’йҖІеҢ–гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгӮ’жңҖеӨ§еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ