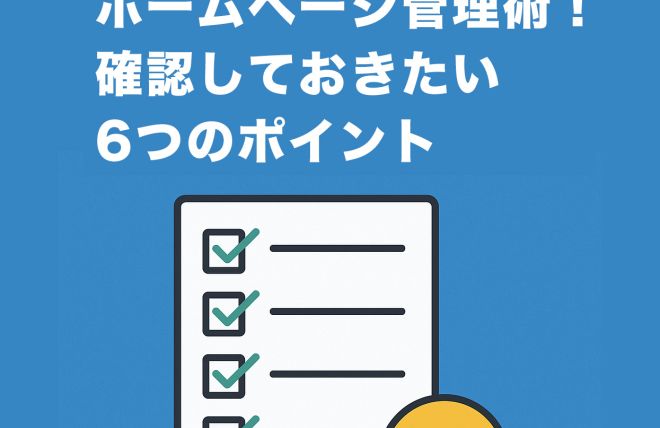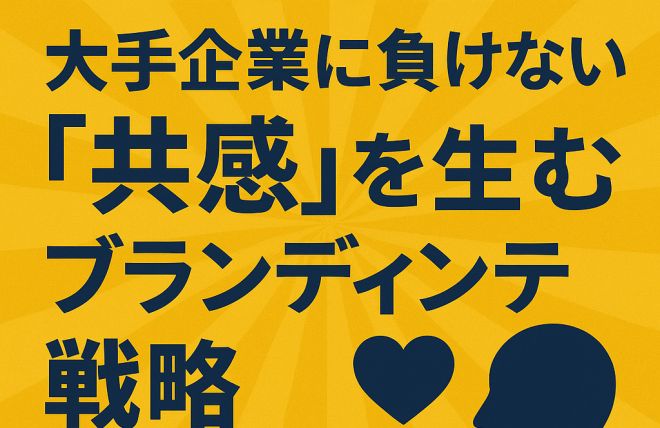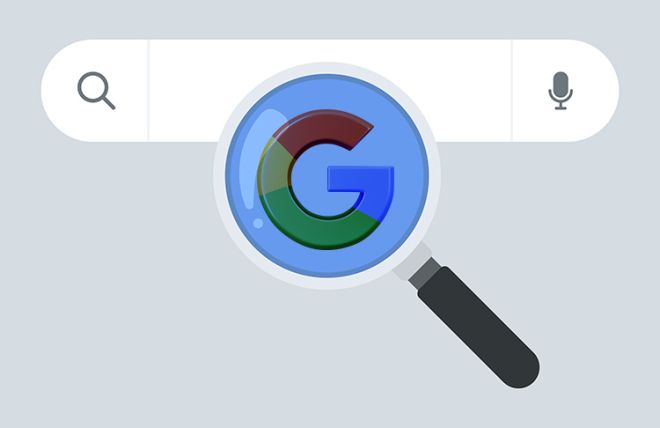йӣўи„ұгӮ’йҳІгҒҗйҚөгҒҜгҖҢйҖҹгҒ•гҖҚгҖӮз”»еғҸжңҖйҒ©еҢ–гҖҒгӮӯгғЈгғғгӮ·гғҘгҖҒгӮігғјгғүж•ҙзҗҶгҖҒгӮөгғјгғҗгғј/CDNиҰӢзӣҙгҒ—гҖҒиЁҲжё¬KPIгҒҫгҒ§гҖҒд»Ҡж—ҘгҒӢгӮүе®ҹи·өгҒ§гҒҚгӮӢиЎЁзӨәйҖҹеәҰж”№е–„гҒ®жүӢй ҶгҒЁгғҒгӮ§гғғгӮҜгғқгӮӨгғігғҲгӮ’и©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
第1з« : гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘзҗҶз”ұ
иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢгғҰгғјгӮ¶гғјгӮЁгӮҜгӮ№гғҡгғӘгӮЁгғігӮ№гҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝ
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгӮЁгӮҜгӮ№гғҡгғӘгӮЁгғігӮ№гҒ«зӣҙзөҗгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒ§гҒҷгҖӮWebгғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢйҖҹгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒҜгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гҒӘгҒҸгӮігғігғҶгғігғ„гҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгҖҒгғқгӮёгғҶгӮЈгғ–гҒӘдҪ“йЁ“гӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒ„е ҙеҗҲгҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒҜгҒқгҒ®гғҡгғјгӮёгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢж„Ҹж¬ІгӮ’еӨұгҒ„гҖҒйӣўи„ұгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гғўгғҗгӮӨгғ«гғҰгғјгӮ¶гғјгҒ§гҒҜгҖҒGoogleгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгғҡгғјгӮёгҒ®иӘӯгҒҝиҫјгҒҝгҒҢ3з§’гӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒЁ53%гҒҢйӣўи„ұгҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгӮ’йҖғгҒ•гҒӘгҒ„иЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒжәҖи¶іеәҰгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢйҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
SEOгӮ„жӨңзҙўгӮЁгғігӮёгғігҒӢгӮүгҒ®и©•дҫЎгҒёгҒ®еҪұйҹҝ
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҜгҖҒSEOпјҲжӨңзҙўгӮЁгғігӮёгғіжңҖйҒ©еҢ–пјүгҒ«гӮӮеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮGoogleгҒҜ2018е№ҙгҒ®гӮ№гғ”гғјгғүгӮўгғғгғ—гғҮгғјгғҲгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғўгғҗгӮӨгғ«жӨңзҙўзөҗжһңгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғҡгғјгӮёйҖҹеәҰгӮ’гғ©гғігӮӯгғігӮ°иҰҒзҙ гҒЁгҒ—гҒҰжҺЎз”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒйҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒҜжӨңзҙўй ҶдҪҚгҒҢдёӢгҒҢгӮҠгҖҒжӨңзҙўгӮЁгғігӮёгғігҒӢгӮүгҒ®жөҒе…ҘгӮӮжёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжӨңзҙўгӮЁгғігӮёгғігҒ®гӮҜгғӯгғјгғ©гғјгҒҜиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒ®йҒ…гҒ„гӮөгӮӨгғҲгӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«е·ЎеӣһгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒгғҡгғјгӮёгҒ®гӮӨгғігғҮгғғгӮҜгӮ№еҢ–гҒҢйҒ…гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒӢгӮүгҒ®зҷәиҰӢзҺҮгҒҢдёӢгҒҢгӮҠгҖҒгғҲгғ©гғ•гӮЈгғғгӮҜгҒ«жӮӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
еЈІдёҠгӮ„гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгҒёгҒ®зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘгӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲ
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҜгҖҒеЈІдёҠгӮ„гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгҒёгҒ®еҪұйҹҝгӮӮз„ЎиҰ–гҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢгӮҸгҒҡгҒӢ1з§’ж”№е–„гҒ•гӮҢгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгҒҢеӨ§е№…гҒ«еҗ‘дёҠгҒ—гҖҒеҸҺзӣҠгӮўгғғгғ—гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮеӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮйҖҶгҒ«гҖҒиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒ„е ҙеҗҲгҒҜгӮ«гғјгғҲж”ҫжЈ„зҺҮгҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҖҒECгӮөгӮӨгғҲгҒ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘжҗҚеӨұгӮ’з”ҹгӮҖеҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғҡгғјгӮёгҒ®иӘӯгҒҝиҫјгҒҝгҒҢ1з§’гҒӢгӮү5з§’гҒҫгҒ§йҒ…гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгҒҢжңҖеӨ§90%дҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгғҮгғјгӮҝгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢж–№жі•гӮ’е®ҹи·өгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзӣҙжҺҘзҡ„гҒ«гғ“гӮёгғҚгӮ№жҲҗжһңгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒ„е ҙеҗҲгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘгғҮгғЎгғӘгғғгғҲ
гҖҖиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒ„е ҙеҗҲгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгӮ„гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒёгҒ®жӮӘеҪұйҹҝгҒҢйЎ•и‘—гҒ«иЎЁгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒ®йӣўи„ұзҺҮгҒҢдёҠгҒҢгӮҠгҖҒгӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ®з¶ҷз¶ҡжҷӮй–“гҒҢзҹӯгҒҸгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮөгӮӨгғҲе…ЁдҪ“гҒ®гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒSEOгҒ®иҰізӮ№гҒ§гӮӮгҖҒйҒ…гҒ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒҜжӨңзҙўй ҶдҪҚгҒҢдёӢгҒҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ競еҗҲгӮөгӮӨгғҲгҒ«гғҰгғјгӮ¶гғјгӮ’еҘӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғігҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғ–гғ©гғігғүгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ«гӮӮжӮӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гғўгғҗгӮӨгғ«гғ•гӮЎгғјгӮ№гғҲгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҖҹеәҰж”№е–„гӮ’жҖ гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№е…ЁдҪ“гҒ®жҲҗеҠҹгӮ’еҰЁгҒ’гӮӢйҮҚеӨ§гҒӘиҰҒеӣ гҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮ
第2з« : иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒ®иЁҲжё¬ж–№жі•гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гӮҲгҒҶ
PageSpeed InsightsгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹеҹәжң¬зҡ„гҒӘгғҒгӮ§гғғгӮҜ
гҖҖGoogleгҒҢжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢз„Ўж–ҷгғ„гғјгғ«гҖҢPageSpeed InsightsгҖҚгҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жңҖгӮӮдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„ж–№жі•гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғ„гғјгғ«гҒҜгҖҒURLгӮ’е…ҘеҠӣгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гғҮгӮ№гӮҜгғҲгғғгғ—гҒЁгғўгғҗгӮӨгғ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҖҹеәҰгӮ№гӮігӮўгӮ’з®—еҮәгҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘж”№е–„гғқгӮӨгғігғҲгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгӮ№гӮігӮўгҒҜ0гҒӢгӮү100гҒҫгҒ§гҒ®зҜ„еӣІгҒ§и©•дҫЎгҒ•гӮҢгҖҒж•°еҖӨгҒҢй«ҳгҒ„гҒ»гҒ©йҖҹеәҰгҒҢжңҖйҒ©еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№жҢҮжЁҷгҒ§гҒӮгӮӢLCPпјҲжңҖеӨ§гӮігғігғҶгғігғ„иЎЁзӨәжҷӮй–“пјүгӮ„FIDпјҲеҲқеӣһе…ҘеҠӣйҒ…延пјүгҒӘгҒ©гҒ®и©ізҙ°гӮӮзўәиӘҚеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖPageSpeed InsightsгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгӮ’йҖғгҒ•гҒӘгҒ„гӮөгӮӨгғҲдҪңгӮҠгҒ«ж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„гғ„гғјгғ«гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒж”№е–„гҒ®е„Әе…ҲдәӢй …гҒҢжҳҺзўәгҒ«зӨәгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҲқеҝғиҖ…гҒӢгӮүдёҠзҙҡиҖ…гҒҫгҒ§е№…еәғгҒҸжҙ»з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒGoogleгҒҢзӣҙжҺҘжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғ„гғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒSEOгҒёгҒ®еҪұйҹҝгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҹзөҗжһңгӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гӮӮеӨ§гҒҚгҒӘйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®д»–гҒ®гғ„гғјгғ« (GTmetrix, WebPageTestгҒӘгҒ©) гҒ®жҙ»з”Ё
гҖҖPageSpeed InsightsгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒд»–гҒ«гӮӮгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғ„гғјгғ«гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҢGTmetrixгҖҚгҒЁгҖҢWebPageTestгҖҚгҒҜеӨҡгҒҸгҒ®гғҰгғјгӮ¶гғјгҒ«ж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖGTmetrixгҒҜгҖҒи©ізҙ°гҒӘгғ¬гғқгғјгғҲгҒЁгӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгғҡгғјгӮёгҒ®иӘӯгҒҝиҫјгҒҝгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®гӮҝгӮӨгғ гғ©гӮӨгғігӮ’иҰ–иҰҡеҢ–гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ©гҒ®ж®өйҡҺгҒ§йҒ…延гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зү№е®ҡгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮWebPageTestгҒҜеӨҡең°еҹҹгҒӢгӮүгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ„гҖҒеӢ•з”»еҪўејҸгҒ§гҒ®иӘӯгҒҝиҫјгҒҝйҒҺзЁӢгҒ®иҰ–иҰҡеҢ–гӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®жҺҘз¶ҡз’°еўғгҒ«еҝңгҒҳгҒҹйҖҹеәҰж”№е–„гҒ®гғ’гғігғҲгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғ„гғјгғ«гӮ’дҪөз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠеӨҡи§’зҡ„гҒ«гӮөгӮӨгғҲгҒ®иӘІйЎҢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒйҖҹеәҰж”№е–„гҒ®ж–№жі•гӮ’еҠ№зҺҮзҡ„гҒ«жҺўгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
иЁҲжё¬й …зӣ®гҒ®и§ЈйҮҲпјҡLCP, FID, CLS гҒ®йҮҚиҰҒжҖ§
гҖҖиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжҢҮжЁҷгҒ§зү№гҒ«жіЁзӣ®гҒҷгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒҢгҖҒCore Web VitalsгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢLCPпјҲжңҖеӨ§гӮігғігғҶгғігғ„иЎЁзӨәжҷӮй–“пјүгҖҒFIDпјҲеҲқеӣһе…ҘеҠӣйҒ…延пјүгҖҒCLSпјҲзҙҜз©Қгғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгӮ·гғ•гғҲпјүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖLCPгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢй–ІиҰ§еҸҜиғҪгҒ гҒЁиӘҚиӯҳгҒҷгӮӢдё»иҰҒгӮігғігғҶгғігғ„гҒҢз”»йқўгҒ«иЎЁзӨәгҒ•гӮҢгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жҷӮй–“гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж•°еҖӨгҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢжңҖеҲқгҒ®еҚ°иұЎгҒ§гҖҢйҒ…гҒ„гӮөгӮӨгғҲгҒ гҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгҖҒйӣўи„ұгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮFIDгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢжңҖеҲқгҒ«гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғігӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®гғ¬гӮ№гғқгғігӮ№жҷӮй–“гӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮӨгғігӮҝгғ©гӮҜгғҶгӮЈгғ–жҖ§гҒ®йҒ…延гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гӮөгӮӨгғҲгҒ§гҒҜгҖҒеҲ©з”ЁдҪ“йЁ“гҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰCLSгҒҜгҖҒгғҡгғјгӮёгҒҢиӘӯгҒҝиҫјгҒҫгӮҢгӮӢйҒҺзЁӢгҒ§зҷәз”ҹгҒҷгӮӢдәҲжңҹгҒ—гҒӘгҒ„гғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгҒ®еӨүеҢ–гӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢжҢҮжЁҷгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҢҮжЁҷгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјдҪ“йЁ“гӮ„SEOгҒ«зӣҙжҺҘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҖӨгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒЁеҲ©дҫҝжҖ§гҒ®дёЎж–№гӮ’й«ҳгӮҒгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®йӣўи„ұгӮ’йҳІгҒҗгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒҘгҒҸгӮҠгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иЁҲжё¬зөҗжһңгҒӢгӮүе„Әе…Ҳж”№е–„гғқгӮӨгғігғҲгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢж–№жі•
гҖҖиЁҲжё¬зөҗжһңгҒӢгӮүгҒ©гҒ®йғЁеҲҶгӮ’е„Әе…Ҳзҡ„гҒ«ж”№е–„гҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’и§ЈйҮҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘйҖҹеәҰж”№е–„гҒ®йҮҚиҰҒгҒӘ第дёҖжӯ©гҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒPageSpeed InsightsгӮ„д»–гҒ®гғ„гғјгғ«гҒҢзӨәгҒҷжҺЁеҘЁдәӢй …гӮ’еҹәгҒ«гҖҒзү№гҒ«ж•°еҖӨгҒҢжҘөз«ҜгҒ«жӮӘгҒ„й …зӣ®гҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒLCPгҒҢй«ҳгҒ„е ҙеҗҲгҒҜз”»еғҸгҒ®жңҖйҒ©еҢ–пјҲең§зё®гӮ„гғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ®еӨүжӣҙпјүгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮFIDгҒҢе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒJavaScriptгҒ®жңҖе°ҸеҢ–гӮ„дёҚиҰҒгҒӘгӮігғјгғүгҒ®еүҠйҷӨгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒCLSгҒ®еҖӨгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгӮігғігғҶгғігғ„гӮ„еәғе‘ҠгҒ®гӮөгӮӨгӮәгӮ’дәӢеүҚгҒ«жұәе®ҡгҒ—гҒҰиҰ–иҰҡзҡ„гҒӘе®үе®ҡжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҖҒиӨҮж•°гҒ®иЁҲжё¬гғ„гғјгғ«гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒе…ұйҖҡгҒ—гҒҰжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢиӘІйЎҢгӮ’жҙ—гҒ„еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®йҖҹеәҰж”№е–„гҒ«е„Әе…Ҳй ҶдҪҚгӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиЁҲжё¬зөҗжһңгӮ’е…ғгҒ«иЁҲз”»зҡ„гҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӢгҒӨиЁҲз”»зҡ„гҒ«йҖҹеәҰж”№е–„гӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
第3з« : гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒ®ж”№е–„гғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜ
з”»еғҸгҒ®жңҖйҒ©еҢ–пјҡгӮөгӮӨгӮәгҒ®ең§зё®гҒЁгғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒ®жңҖйҒ©еҢ–
гҖҖз”»еғҸгҒҜгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢиҰҒеӣ гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮз”»еғҸгӮөгӮӨгӮәгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁгҖҒгғҡгғјгӮёгҒ®иӘӯгҒҝиҫјгҒҝйҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®йӣўи„ұгӮ’жӢӣгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҖҹеәҰж”№е–„гҒ®з¬¬дёҖжӯ©гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз”»еғҸгҒ®жңҖйҒ©еҢ–гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҖе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒз”»еғҸгғ•гӮЎгӮӨгғ«гҒ®ең§зё®гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгғ•гӮЎгӮӨгғ«гӮөгӮӨгӮәгӮ’е°ҸгҒ•гҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮз„Ўж–ҷгҒ®гғ„гғјгғ«гҒ§гҒӮгӮӢSquooshгӮ„TinyPNGгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз”»иіӘгӮ’гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жҗҚгҒӘгҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸең§зё®гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒWebPгҒӘгҒ©гҒ®жңҖж–°гғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ•гӮүгҒ«и»ҪйҮҸгҒӘз”»еғҸгӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖз”»еғҸжңҖйҒ©еҢ–гҒҜгҖҢгғҰгғјгӮ¶гғјгӮ’йҖғгҒ•гҒӘгҒ„пјҒгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гҒӢгӮүйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢж–№жі•гҒ®дёӯгҒ§жңҖгӮӮжүӢи»ҪгҒ§еҠ№жһңзҡ„гҒӘеҜҫзӯ–гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӯгғЈгғғгӮ·гғҘгҒ®жҙ»з”ЁгҒ§гғҡгғјгӮёиӘӯгҒҝиҫјгҒҝгӮ’й«ҳйҖҹеҢ–
гҖҖгғ–гғ©гӮҰгӮ¶гӮӯгғЈгғғгӮ·гғҘгҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’иЁӘгӮҢгҒҹгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®з«Ҝжң«гҒ«гғҮгғјгӮҝгӮ’дёҖжҷӮзҡ„гҒ«дҝқеӯҳгҒ—гҖҒж¬ЎеӣһиЁӘе•ҸжҷӮгҒ«гҒқгӮҢгӮ’еҶҚеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒЁгҒ®йҖҡдҝЎйҮҸгҒҢжёӣе°‘гҒ—гҖҒгғҡгғјгӮёгҒ®иӘӯгҒҝиҫјгҒҝйҖҹеәҰгҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгӮӯгғЈгғғгӮ·гғҘгҒ®иЁӯе®ҡгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒҢеҶҚеәҰеҗҢгҒҳгғҡгғјгӮёгӮ’иЁӘгӮҢгҒҹйҡӣгҒ«гҖҒиЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’еӨ§е№…гҒ«ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮӯгғЈгғғгӮ·гғҘгҒ®жңүеҠ№жңҹйҷҗгӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҖҒз”»еғҸгӮ„CSSгғ•гӮЎгӮӨгғ«гҒӘгҒ©гҒ®йқҷзҡ„гӮігғігғҶгғігғ„гӮ’еҶҚгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒӣгҒҡгҒ«еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж»һеңЁжҷӮй–“гӮ’еў—гӮ„гҒ—гҖҒйӣўи„ұзҺҮгӮ’дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгӮӢеҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғјгғҗгғјгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒЁгғӣгӮ№гғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—
гҖҖгӮөгғјгғҗгғјгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ„гғӣгӮ№гғҶгӮЈгғігӮ°гғ—гғ©гғігҒ®е“ҒиіӘгҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒиЁӘе•ҸиҖ…ж•°гҒҢеӨҡгҒ„гӮөгӮӨгғҲгҒ§гҒҜгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒ®жҖ§иғҪдёҚи¶ігҒҢеҺҹеӣ гҒ§гғҡгғјгӮёиЎЁзӨәгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖеҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгӮҠй«ҳйҖҹгҒӘгӮөгғјгғҗгғјгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгҒҹгӮҠгҖҒеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰе°Ӯз”ЁгӮөгғјгғҗгғјгӮ„гӮҜгғ©гӮҰгғүгғӣгӮ№гғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гӮўгғғгғ—гӮ°гғ¬гғјгғүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮөгғјгғҗгғјеҒҙгҒ§gzipең§зё®гӮ’жңүеҠ№еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҡгғјгӮёгғӯгғјгғүйҖҹеәҰгҒ®еҗ‘дёҠгӮӮеӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж–№жі•гҒ§гӮөгғјгғҗгғјиІ иҚ·гӮ’и»ҪжёӣгҒ—гҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒ«гӮ№гғ гғјгӮәгҒӘдҪ“йЁ“гӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҚиҰҒгҒӘгғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігӮ„гӮ№гӮҜгғӘгғ—гғҲгҒ®еүҠйҷӨ
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®йҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒ„зҗҶз”ұгҒ®дёҖгҒӨгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒ®гҒӘгҒ„гғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігӮ„гӮ№гӮҜгғӘгғ—гғҲгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒCMSпјҲгӮігғігғҶгғігғ„з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ пјүгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒеӨҡж•°гҒ®гғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігҒҢгӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгғңгғҲгғ«гғҚгғғгӮҜгҒЁгҒӘгӮҠиЎЁзӨәгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігӮ„йҮҚиӨҮгҒҷгӮӢж©ҹиғҪгӮ’жҢҒгҒӨгғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігӮ’еүҠйҷӨгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮгҖҒеӨ§е№…гҒӘйҖҹеәҰж”№е–„гҒҢиҰӢиҫјгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒJavaScriptгӮ„CSSгҒ®дёҚиҰҒгҒӘгӮігғјгғүгӮ’еүҠйҷӨгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢгҒ•гӮүгҒ«еҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжӨңзҙўгӮЁгғігӮёгғігҒӢгӮүгҒ®и©•дҫЎгӮӮеҗ‘дёҠгҒ—гҖҒй–“жҺҘзҡ„гҒӘSEOеҠ№жһңгӮӮеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
CDN (Content Delivery Network) гҒ®е°Һе…ҘгғЎгғӘгғғгғҲ
гҖҖиЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒCDNпјҲContent Delivery NetworkпјүгҒ®е°Һе…ҘгҒҜйқһеёёгҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮCDNгҒЁгҒҜгҖҒгӮҰгӮ§гғ–гӮігғігғҶгғігғ„гӮ’иӨҮж•°гҒ®гӮөгғјгғҗгғјгҒ«еҲҶж•ЈгҒ•гҒӣгҖҒең°зҗҶзҡ„гҒ«жңҖгӮӮиҝ‘гҒ„гӮөгғјгғҗгғјгҒӢгӮүгғҮгғјгӮҝгӮ’й…ҚдҝЎгҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгҒ©гҒ“гҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеқҮдёҖгҒӘйҖҹеәҰгҒ§гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’иЎЁзӨәгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖзү№гҒ«гҖҒжө·еӨ–гҒӢгӮүгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢеӨҡгҒ„е ҙеҗҲгӮ„еӨ§йҮҸгҒ®гғҲгғ©гғ•гӮЈгғғгӮҜгӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒCDNгҒ®е°Һе…ҘгҒҜйҖҹеәҰж”№е–„гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸиІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒCloudflareгӮ„AWS CDNгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒйҖҹеәҰеҗ‘дёҠгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгӮөгғјгғҗгғјиІ иҚ·гҒ®и»ҪжёӣгӮ„гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеј·еҢ–гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғЎгғӘгғғгғҲгӮӮдә«еҸ—гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјжәҖи¶іеәҰгӮ’й«ҳгӮҒгҖҒйӣўи„ұзҺҮгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢеҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
第4з« : ж”№е–„еҫҢгҒ®жҲҗжһңгӮ’жңҖеӨ§еҢ–гҒҷгӮӢж–№жі•
з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒ§жңҖйҒ©еҢ–зҠ¶ж…ӢгӮ’з¶ӯжҢҒ
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’дёҖеәҰж”№е–„гҒ—гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§е®үеҝғгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒжҷӮй–“гҒ®зөҢйҒҺгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еҠ№жһңгҒҢи–„гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж–°гҒ—гҒ„з”»еғҸгӮ„гӮ№гӮҜгғӘгғ—гғҲгҒ®иҝҪеҠ гҖҒгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ®жӣҙж–°гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮGoogle PageSpeed InsightsгӮ„GTmetrixгҒӘгҒ©гҒ®гғ„гғјгғ«гӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒ«дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰжё¬е®ҡгҒ—гҖҒйҖҹеәҰж”№е–„гҒ®зҠ¶жіҒгӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒCore Web VitalsгҒ®жҢҮжЁҷгҒ§гҒӮгӮӢLCPгҖҒFIDгҖҒCLSгҒӘгҒ©гӮ’иҝҪи·ЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжңҖйҒ©еҢ–зҠ¶ж…ӢгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгӮ’йҖғгҒ•гҒӘгҒ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёйҒӢе–¶гҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
A/BгғҶгӮ№гғҲгҒ§еҠ№жһңзҡ„гҒӘйҖҹеәҰж”№е–„зӯ–гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢ
гҖҖйҖҹеәҰж”№е–„гҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢе®ҹйҡӣгҒ«гғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒӢгӮ’жӨңиЁјгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«жңүеҠ№гҒӘгҒ®гҒҢA/BгғҶгӮ№гғҲгҒ§гҒҷгҖӮеҗҢгҒҳгғҡгғјгӮёгҒ®иӨҮж•°гғҗгғјгӮёгғ§гғігӮ’гғҶгӮ№гғҲгҒ—гҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒ®ж–№гҒҢй«ҳгҒ„гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгӮ„й•·гҒ„ж»һеңЁжҷӮй–“гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷгҒӢгӮ’жҜ”ијғгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒз”»еғҸгҒ®ең§зё®гғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҹгғҗгғјгӮёгғ§гғігҒЁеӨүжӣҙгҒ—гҒӘгҒ„гғҗгғјгӮёгғ§гғігӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒҢиЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒЁгғҰгғјгӮ¶гғјгӮЁгӮҜгӮ№гғҡгғӘгӮЁгғігӮ№гҒ«иүҜгҒ„еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒӢгӮ’еҲҶжһҗгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғҮгғјгӮҝгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹж–№жі•гҒ§йҖҹеәҰж”№е–„гҒ®жҲҗжһңгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ•гӮүгҒӘгӮӢжңҖйҒ©еҢ–гҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гғҮгғјгӮҝгҒ®еҲҶжһҗгҒ§иӘІйЎҢгӮ’зү№е®ҡ
гҖҖGoogle AnalyticsгӮ„гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гғ„гғјгғ«гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гғҮгғјгӮҝгӮ’и©ігҒ—гҒҸеҲҶжһҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйҖҹеәҰгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиӘІйЎҢгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒзӣҙеё°зҺҮгӮ„йӣўи„ұзҺҮгҒҢзү№е®ҡгҒ®гғҡгғјгӮёгҒ§й«ҳгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®гғҡгғјгӮёгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгҒ«е•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ©гҒ®гғҮгғҗгӮӨгӮ№гӮ„гғ–гғ©гӮҰгӮ¶гҒ§гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гҒҢжӮӘеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зү№е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҮгғјгӮҝгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹеҲҶжһҗгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйҖҹеәҰж”№е–„гҒҢдёҖеұӨеҠ№жһңзҡ„гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјжәҖи¶іеәҰгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
競еҗҲгӮөгӮӨгғҲгҒЁгҒ®жҜ”ијғгҒ§ж¬ЎгҒ®ж”№е–„гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’иЁҲз”»
гҖҖ競еҗҲгӮөгӮӨгғҲгҒ®иЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’еҲҶжһҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиҮӘзӨҫгӮөгӮӨгғҲгҒҢгҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒ®гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ’йҒ”жҲҗгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮGTmetrixгӮ„WebPageTestгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰ競еҗҲгӮөгӮӨгғҲгӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еј·гҒҝгӮ„ејұгҒҝгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ競еҗҲгҒҢCDNгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰиЎЁзӨәйҖҹеәҰгӮ’й«ҳйҖҹеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒиҮӘзӨҫгҒ§гӮӮеҗҢж§ҳгҒ®жүӢжі•гӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§е·®гӮ’зё®гӮҒгӮүгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з«¶еҗҲеҲҶжһҗгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж¬ЎгҒ®ж”№е–„гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’иЁҲз”»гҒҷгӮӢйҡӣгҒ®жңүеҠ№гҒӘжҢҮйҮқгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ