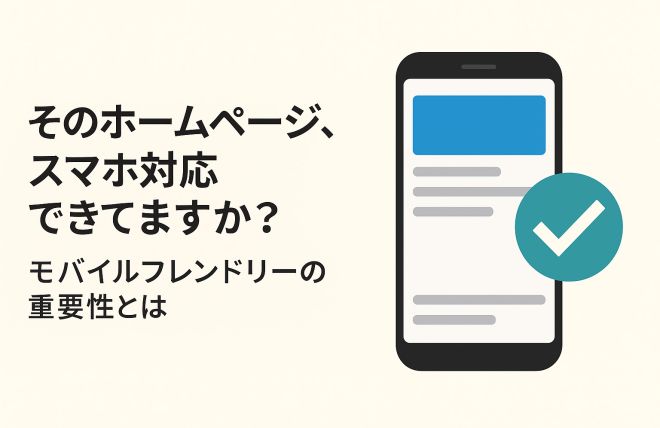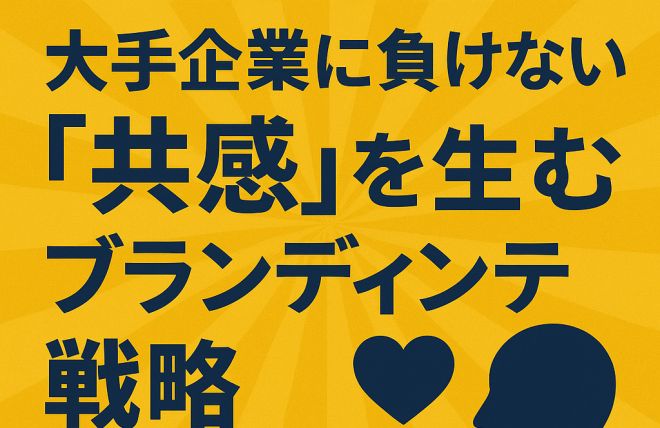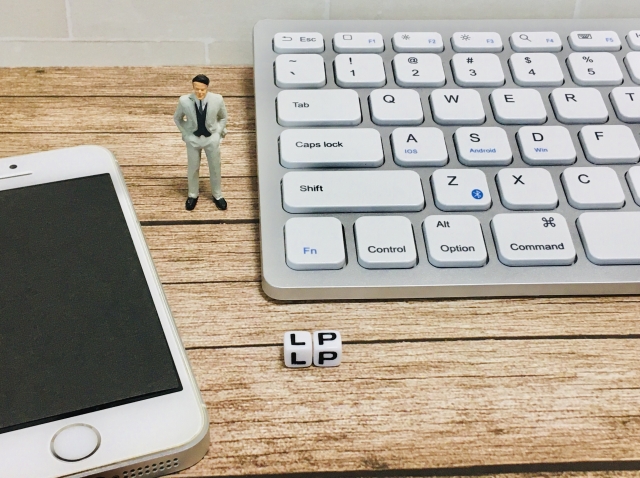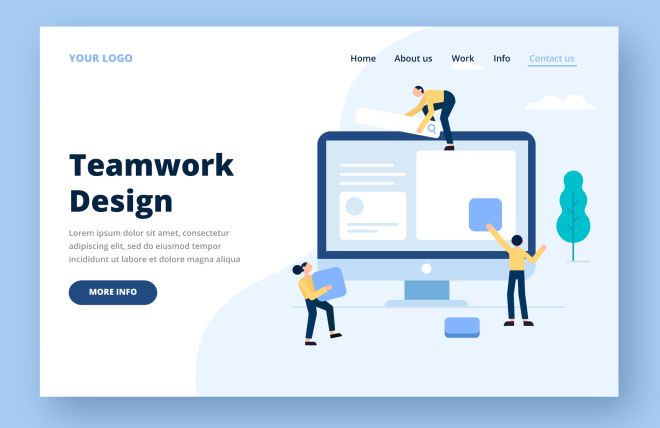гғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гӮ’еҸҜиҰ–еҢ–гҒҷгӮӢгҖҢгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгҖҚгҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёж”№е–„гҒ«дёҚеҸҜж¬ гҖӮеҹәжң¬гҒӢгӮүе°Һе…ҘгғЎгғӘгғғгғҲгҖҒжҙ»з”Ёжі•гҒҫгҒ§и©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮжңҖеӨ§еҢ–гҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®еҹәзӨҺзҹҘиӯҳ
гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒЁгҒҜпјҹеҹәжң¬зҡ„гҒӘд»•зө„гҒҝгҒЁзҗҶи§Ј
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒЁгҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ„WebгӮөгӮӨгғҲдёҠгҒ®гғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гӮ’еҸҜиҰ–еҢ–гҒҷгӮӢгғ„гғјгғ«гҒ§гҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®гғһгӮҰгӮ№гҒ®еӢ•гҒҚгӮ„гӮҜгғӘгғғгӮҜдҪҚзҪ®гҖҒгӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гҒ®ж·ұгҒ•гҒӘгҒ©гӮ’иүІгҒ§зӣҙж„ҹзҡ„гҒ«зӨәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮиөӨгӮ„гӮӘгғ¬гғігӮёгҒӘгҒ©гҒ®иүІгҒҢжҝғгҒ„гҒ»гҒ©гҖҒгҒқгҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒҢгӮҲгҒҸеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®иӘІйЎҢгӮ’з°ЎеҚҳгҒ«жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘж”№е–„ж–Ҫзӯ–гӮ’иҖғжЎҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгҒҜгҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®иЁӘе•ҸиҖ…гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮөгӮӨгғҲгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒгҒ©гҒ“гҒ§иҝ·гҒ„гҖҒгҒ©гҒ“гҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮ’иҰ–иҰҡзҡ„гҒ«жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгҒҹгҒ„гӮөгӮӨгғҲйҒӢе–¶иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеј·еҠӣгҒӘгғ„гғјгғ«гҒ§гҒҷгҖӮ
зЁ®йЎһеҲҘгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®зү№еҫҙгҒЁз”ЁйҖ”
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ«гҒҜгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®зЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢз•°гҒӘгӮӢзү№еҫҙгҒЁз”ЁйҖ”гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ1. гӮўгғҶгғігӮ·гғ§гғіпјҲзҶҹиӘӯпјүгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—пјҡгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгҒ©гҒ®гӮЁгғӘгӮўгӮ’зҶҹиӘӯгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’иҰ–иҰҡеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғҶгӮӯгӮ№гғҲгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢй ҳеҹҹгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒйҮҚиҰҒгҒӘгӮігғігғҶгғігғ„гӮ’йҒ©еҲҮгҒӘдҪҚзҪ®гҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢйҡӣгҒ«еҪ№з«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ2. гӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—пјҡгғҡгғјгӮёгҒ®гҒ©гҒ®йғЁеҲҶгҒҫгҒ§гӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®еӨҡгҒҸгҒҢйӣўи„ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢең°зӮ№гӮ’зү№е®ҡгҒ—гҖҒж”№е–„ж–Ҫзӯ–гӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ3. гӮҜгғӘгғғгӮҜгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—пјҡгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢе®ҹйҡӣгҒ«гӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ—гҒҹз®ҮжүҖгӮ’еҸҜиҰ–еҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдё»иҰҒгҒӘгғңгӮҝгғігӮ„гғӘгғігӮҜгҒ®гӮҜгғӘгғғгӮҜзҺҮгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒCTAпјҲCall to ActionпјүгҒ®жңҖйҒ©еҢ–гӮ’еӣігӮӢйҡӣгҒ«жҙ»з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ4. гғһгӮҰгӮ№гғ гғјгғ–гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—пјҡгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®гғһгӮҰгӮ№гҒ®и»Ңи·ЎгӮ’иЁҳйҢІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғһгӮҰгӮ№гҒ®еӢ•гҒҚгҒ«гҒҜгҖҒиҰ–з·ҡгҒЁгҒ®й«ҳгҒ„зӣёй–ўгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮЁгғӘгӮўгӮ’жҺЁжё¬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгҒ®зЁ®йЎһгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гӮ’еӨҡи§’зҡ„гҒ«еҲҶжһҗгҒ—гҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®жңҖйҒ©еҢ–гҒ«жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢдё»гҒӘеҲҶжһҗжҢҮжЁҷ
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜгҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®еҲҶжһҗгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰд»ҘдёӢгҒ®дё»гҒӘжҢҮжЁҷгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ1. гӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ®еҲҶеёғпјҡгҒ©гҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒҢжңҖгӮӮгӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғңгӮҝгғій…ҚзҪ®гӮ„гғӘгғігӮҜгҒ®еҠ№жһңгӮ’жё¬е®ҡеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖ2. гӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«зҺҮпјҡгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгғҡгғјгӮёгҒ®гҒ©гҒ“гҒҫгҒ§гӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гҒ—гҒҹгҒӢгӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’е…ғгҒ«гҖҒгӮігғігғҶгғігғ„гҒ®й…ҚзҪ®гӮ„гғҡгғјгӮёж§ӢжҲҗгӮ’иҰӢзӣҙгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ3. й–ІиҰ§гӮЁгғӘгӮўпјҡгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢе®ҹйҡӣгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҜ„еӣІгӮ’зү№е®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮігғігғҶгғігғ„гҒ®е„Әе…Ҳй ҶдҪҚд»ҳгҒ‘гҒҢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖ4. йӣўи„ұгӮЁгғӘгӮўпјҡгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгғҡгғјгӮёгӮ’йӣўгӮҢгӮӢгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„е ҙжүҖгӮ’жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮйӣўи„ұгғқгӮӨгғігғҲгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®ж»һеңЁжҷӮй–“гӮ’延гҒ°гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҢҮжЁҷгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®WebгӮөгӮӨгғҲдёҠгҒ§гҒ®иЎҢеӢ•гғ‘гӮҝгғјгғігӮ’и©ізҙ°гҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®ж”№е–„гҒ«еҪ№з«ӢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
жҠјгҒ•гҒҲгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„гғ„гғјгғ«гҒ®йҒёгҒіж–№
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гғ„гғјгғ«гӮ’йҒёгҒ¶йҡӣгҒ«гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖ1. еҲҶжһҗгҒ—гҒҹгҒ„жҢҮжЁҷгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢпјҡгӮҜгғӘгғғгӮҜгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ„гӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒӘгҒ©гҖҒйҒ”жҲҗгҒ—гҒҹгҒ„зӣ®зҡ„гҒ«еҗҲгҒЈгҒҹж©ҹиғҪгҒҢжҸғгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҖ2. дҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ•пјҡгғ„гғјгғ«гҒ®гӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№гҒҢзӣҙж„ҹзҡ„гҒ§гӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒӢгҒҜйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮж“ҚдҪңгҒҢиӨҮйӣ‘гҒ гҒЁеҲҶжһҗгҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҖҒжҙ»з”ЁгҒҢйҖІгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҖ3. д»–гҒ®гғ„гғјгғ«гҒЁгҒ®йҖЈжҗәпјҡGoogleгӮўгғҠгғӘгғҶгӮЈгӮҜгӮ№гҒӘгҒ©гҖҒд»–гҒ®Webи§Јжһҗгғ„гғјгғ«гҒЁйҖЈжҗәгҒ§гҒҚгӮӢж©ҹиғҪгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгғҮгғјгӮҝгӮ’еӨҡи§’зҡ„гҒ«жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖ4. з„Ўж–ҷзүҲгҒЁжңүж–ҷзүҲгҒ®жҜ”ијғпјҡз„Ўж–ҷгғ„гғјгғ«гҒҜжүӢи»ҪгҒ«е°Һе…ҘгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж©ҹиғҪгҒҢйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңүж–ҷгғ„гғјгғ«гӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒҜгҖҒжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгӮӢдҫЎеҖӨгҒҢдҫЎж јгҒ«иҰӢеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠжҜ”ијғгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҖеҲ©з”Ёз”ЁйҖ”гӮ„дәҲз®—гҒ«еҝңгҒҳгҒҰжңҖйҒ©гҒӘгғ„гғјгғ«гӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҠ№зҺҮгӮҲгҒҸгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгӮ’жҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•еҲҶжһҗгҒ®е…·дҪ“дҫӢ
дәӢдҫӢ1пјҡгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®еҒңж»һгӮЁгғӘгӮўгӮ’зү№е®ҡгҒ—ж”№е–„
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгӮ’дҪҝгҒҶгҒЁгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеҶ…гҒ§гғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢй•·гҒҸж»һеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮЁгғӘгӮўгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢеҒңж»һгӮЁгғӘгӮўгҖҚгӮ’зү№е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®иҲҲе‘ігӮ’еј•гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„йғЁеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢдёҖж–№гҖҒжғ…е ұйҮҸгҒҢйҒҺеӨҡгҒ§гғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢж¬ЎгҒ®иЎҢеӢ•гҒ«з§»гӮҢгҒӘгҒ„еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒй•·гҒҷгҒҺгӮӢгғ•гӮ©гғјгғ гӮ„жғ…е ұгҒ®зҫ…еҲ—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢйӣўи„ұгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ§иӘІйЎҢз®ҮжүҖгӮ’еҸҜиҰ–еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒӘгғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгӮ„жғ…е ұж•ҙзҗҶгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘж”№е–„зӯ–гӮ’ж–ҪгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҒңж»һгӮЁгғӘгӮўгӮ’зү№е®ҡгҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘеҜҫзӯ–гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮеҗ‘дёҠгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢдҫӢ2пјҡгӮігғігғҶгғігғ„гӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«зҺҮгҒ®жҠҠжҸЎгҒЁжңҖйҒ©еҢ–
гҖҖгӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ„WebгӮөгӮӨгғҲгҒ®гҒ©гҒ®йғЁеҲҶгҒҫгҒ§гӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гҒ—гҒҹгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«йқһеёёгҒ«жңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ§гҖҒйҮҚиҰҒгҒӘгӮігғігғҶгғігғ„гҒҢгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ«иӘӯгҒҫгӮҢгҒҡгҒ«еҹӢгӮӮгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«зҺҮгҒҢ50пј…гӮ’дёӢеӣһгӮӢйғЁеҲҶгҒ«е•Ҷе“ҒгҒ®зү№еҫҙгӮ„CTAпјҲCall To ActionпјүгҒҢй…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒгӮігғігғҶгғігғ„гҒ®еҶҚй…ҚзҪ®гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҲҶжһҗгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢйӣўи„ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғқгӮӨгғігғҲгӮ’зү№е®ҡгҒ—гҖҒжғ…е ұгҒ®дёҠйғЁй…ҚзҪ®гӮ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®ж”№е–„гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮігғігғҶгғігғ„гҒёгҒ®й–ўеҝғеәҰгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢдҫӢ3пјҡCTAпјҲCall To ActionпјүгҒ®гӮҜгғӘгғғгӮҜеҲҶжһҗ
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷCTAгҒ®гӮҜгғӘгғғгӮҜдҪҚзҪ®гӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгӮҜгғӘгғғгӮҜгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҢдҫҝеҲ©гҒ§гҒҷгҖӮгӮҜгғӘгғғгӮҜгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’дҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ©гҒ®гғңгӮҝгғігҒҢеӨҡгҒҸгӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒйҖҶгҒ«гӮҜгғӘгғғгӮҜгҒҢе°‘гҒӘгҒ„йғЁеҲҶгҒҜгҒ©гҒ“гҒӘгҒ®гҒӢгӮ’иҰ–иҰҡзҡ„гҒ«зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒCTAгҒҢзӣ®з«ӢгҒҹгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§иЎЁзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®еҲҶжһҗзөҗжһңгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гғңгӮҝгғігҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғіеӨүжӣҙгӮ„й…ҚзҪ®гҒ®иӘҝж•ҙгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒCTAгҒ®еҠ№жһңгӮ’жңҖеӨ§еҢ–гҒ—гҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢдҫӢ4пјҡгғ•гӮЎгғјгӮ№гғҲгғ“гғҘгғјгҒ®жіЁзӣ®еәҰи§Јжһҗ
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гғ•гӮЎгғјгӮ№гғҲгғ“гғҘгғјгҒҢгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘гғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®жіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’и§ЈжһҗгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гғһгӮҰгӮ№гғ гғјгғ–гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ„гӮўгғҶгғігӮ·гғ§гғігғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜгҖҒгғҡгғјгӮёиӘӯгҒҝиҫјгҒҝеҫҢгҒҷгҒҗгҒ«гғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢгҒ©гҒ®йғЁеҲҶгҒ«зӣ®гӮ’еҗ‘гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгғ•гӮЎгғјгӮ№гғҲгғ“гғҘгғјгҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹз”»еғҸгӮ„иҰӢеҮәгҒ—гҒҢеҚҒеҲҶгҒ«жіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгӮӯгғЈгғғгғҒгӮігғ”гғјгӮ„гғ“гӮёгғҘгӮўгғ«гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ第дёҖеҚ°иұЎгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒ®й–ўеҝғгӮ’еј•гҒҚз•ҷгӮҒгҖҒж¬ЎгҒ®гӮігғігғҶгғігғ„гҒёгҒЁиӘҳе°ҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—е°Һе…ҘгҒ®гғҷгӮ№гғҲгғ—гғ©гӮҜгғҶгӮЈгӮ№
е°Һе…ҘеүҚгҒ«жҳҺзўәеҢ–гҒҷгҒ№гҒҚKPIгҒ®иЁӯе®ҡж–№жі•
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒжңҖеҲқгҒ«KPIпјҲйҮҚиҰҒжҘӯзёҫи©•дҫЎжҢҮжЁҷпјүгӮ’жҳҺзўәгҒ«иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮKPIгӮ’иЁӯе®ҡгҒӣгҒҡгҒ«е°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®еҲҶжһҗзөҗжһңгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒӢгҒҢжӣ–жҳ§гҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҠ№жһңзҡ„гҒӘж–Ҫзӯ–гҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӣ®зҡ„гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢзү№е®ҡгғҡгғјгӮёгҒ®CTAгӮҜгғӘгғғгӮҜзҺҮгӮ’10пј…еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘжҢҮжЁҷгӮ’KPIгҒЁгҒ—гҒҰиЁӯе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжҳҺзўәгҒӘгӮҙгғјгғ«гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгӮ’жҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
и§ЈжһҗгҒ®зөҗжһңгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒӘж”№е–„ж–Ҫзӯ–гҒ«иҗҪгҒЁгҒ—иҫјгӮҖж–№жі•
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®и§ЈжһҗзөҗжһңгҒҜгҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®иӘІйЎҢгӮ’зҷәиҰӢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘжғ…е ұгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзөҗжһңгӮ’гҒ©гҒҶж”№е–„ж–Ҫзӯ–гҒ«зөҗгҒігҒӨгҒ‘гӮӢгҒӢгҒҢйҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ§зү№е®ҡгҒ®гӮігғігғҶгғігғ„гӮЁгғӘгӮўгҒ®й–ІиҰ§зҺҮгҒҢдҪҺгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ„й…ҚзҪ®гӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮҜгғӘгғғгӮҜгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ§CTAгҒҢжңҹеҫ…гҒ—гҒҹж•°гӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгғңгӮҝгғігҒ®иүІгӮ„гғҶгӮӯгӮ№гғҲгӮ’еӨүжӣҙгҒ—гҒҰжіЁзӣ®еәҰгӮ’дёҠгҒ’гӮӢж–Ҫзӯ–гҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҫ—гҒҹгғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гҒ®еҸҜиҰ–еҢ–гғҮгғјгӮҝгӮ’еҹәгҒ«гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘж”№е–„гғ—гғ©гғігӮ’з«ӢжЎҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
зӨҫеҶ…гғ»еӨ–йғЁгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгғқгӮӨгғігғҲ
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—е°Һе…ҘгӮ„еҲҶжһҗгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒзӨҫеҶ…гғЎгғігғҗгғјгӮ„еӨ–йғЁгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгӮӮжҲҗеҠҹгҒ®гӮ«гӮ®гҒ§гҒҷгҖӮгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜиҰ–иҰҡзҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒWebй–ӢзҷәжӢ…еҪ“иҖ…гҖҒгғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҖҒгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жӢ…еҪ“иҖ…гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз•°гҒӘгӮӢеҪ№еүІгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒЁгӮӮе…ұжңүгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гғ„гғјгғ«гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеӨ–йғЁгҒ®гӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгӮ„гғ„гғјгғ«гҒ®гӮөгғқгғјгғҲжӢ…еҪ“иҖ…гҒЁйҖЈжҗәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘиҰ–зӮ№гҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒи§ЈйҮҲгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гғҮгғјгӮҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰйҒ©еҲҮгҒӘж–№жі•гҒ§иӘӯгҒҝи§ЈгҒҸгӮөгғқгғјгғҲгӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢзӮ№гҒҜеӨ–йғЁгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒ®еј·гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮ
ж”№е–„гӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ’жңҖеӨ§еҢ–гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®PDCAжүӢжі•
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҠ№жһңгӮ’жңҖеӨ§йҷҗеј•гҒҚеҮәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒPDCAпјҲPlan-Do-Check-ActпјүгӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ’е®ҹи·өгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒиӘІйЎҢгӮ’зү№е®ҡгҒ—гҒҰж”№е–„гғ—гғ©гғігӮ’з«ӢгҒҰпјҲPlanпјүгҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгҒ®зөҗжһңгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰе…·дҪ“зҡ„гҒӘж–Ҫзӯ–гӮ’е®ҹиЎҢпјҲDoпјүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒе®ҹиЎҢгҒ—гҒҹж–Ҫзӯ–гҒ®еҠ№жһңгӮ’еҶҚгҒігғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ§зўәиӘҚгҒ—пјҲCheckпјүгҖҒеҫ—гӮүгӮҢгҒҹзөҗжһңгӮ„иӘІйЎҢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҰж¬ЎгҒ®гӮўгӮҜгӮ·гғ§гғігӮ’иЁҲз”»пјҲActпјүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ’з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒӢгӮүгҒ®е®ҡжҖ§зҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝгҒЁгӮўгӮҜгӮ»гӮ№и§ЈжһҗгҒ®е®ҡйҮҸзҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠзІҫеәҰгҒ®й«ҳгҒ„ж”№е–„ж–Ҫзӯ–гӮ’е°ҺгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиіӘе•ҸгҒЁеӨұж•—дәӢдҫӢгҒӢгӮүеӯҰгҒ¶гғ’гғігғҲ
гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®еҲ©з”ЁгҒ§йҷҘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„иӘӨи§Ј
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜзӣҙж„ҹзҡ„гҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„еҲҶжһҗгғ„гғјгғ«гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҒ©еҲҮгҒ«жҙ»з”ЁгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁиӘӨи§ЈгӮ’з”ҹгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиӘӨи§ЈгҒ®дёҖгҒӨгҒ«гҖҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®е•ҸйЎҢгҒҢгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ§и§ЈжұәгҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘҚиӯҳгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•еҸҜиҰ–еҢ–гҒ®дёҖжүӢж®өгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮўгӮҜгӮ»гӮ№и§ЈжһҗгӮ„гғҰгғјгӮ¶гғјгғӘгӮөгғјгғҒгҒӘгҒ©д»–гҒ®гғҮгғјгӮҝгҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§зңҹдҫЎгӮ’зҷәжҸ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢгғһгӮҰгӮ№гҒ®еӢ•гҒҚгҒҢеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®иҰ–з·ҡгӮ’100%еҸҚжҳ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйҷҗз•ҢгӮӮзҗҶи§ЈгҒҷгҒ№гҒҚгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иӘӨи§ЈгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’дҪҝгҒ„гҒӘгҒҢгӮүд»–гҒ®и§ЈжһҗжүӢжі•гҒЁгӮӮгғҗгғ©гғігӮ№гӮҲгҒҸжҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
жңҹеҫ…гҒҷгӮӢжҲҗжһңгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒ„зҗҶз”ұгҒЁгҒқгҒ®еҜҫзӯ–
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒжңҹеҫ…гҒ—гҒҹжҲҗжһңгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дё»гҒӘеҺҹеӣ гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢеҲҶжһҗгҒ®зӣ®зҡ„гҒҢжӣ–жҳ§гҖҚгҖҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҹгғҮгғјгӮҝгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒӘж”№е–„ж–Ҫзӯ–гҒ«иҗҪгҒЁгҒ—иҫјгӮҒгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒ“гҒЁгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®иӘІйЎҢгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒӣгҒҡгҒ«гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒ©гҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҢйҮҚиҰҒгҒӢгӮҸгҒӢгӮүгҒҡгҖҒж–Ҫзӯ–гӮ’е®ҹиЎҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе°Һе…ҘеүҚгҒ«KPIгӮ„гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒҷгӮӢиӘІйЎҢгӮ’жҳҺзўәеҢ–гҒ—гҖҒгғҮгғјгӮҝгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹгӮўгӮҜгӮ·гғ§гғігғ—гғ©гғігӮ’зӯ–е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҒгғјгғ еҶ…гҒ§гғҮгғјгӮҝгҒ®е…ұжңүгӮ’еј·еҢ–гҒ—гҖҒе…Ёе“ЎгҒҢе…ұйҖҡгҒ®зӣ®жЁҷгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰиЎҢеӢ•еҶ…иЁігӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
з„Ўж–ҷгғ„гғјгғ«гҒЁжңүж–ҷгғ„гғјгғ«гҖҒгҒ©гҒЎгӮүгӮ’йҒёгҒ¶гҒ№гҒҚгҒӢ
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ«гҒҜз„Ўж–ҷгғ„гғјгғ«гҒЁжңүж–ҷгғ„гғјгғ«гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«гғЎгғӘгғғгғҲгҒЁиӘІйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз„Ўж–ҷгғ„гғјгғ«гҒҜе°Һе…ҘгҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҢдҪҺгҒҸгҖҒеҲқгӮҒгҒҰгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгӮ’и©ҰгҒҷе ҙеҗҲгҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж©ҹиғҪгҒҢйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘWebгӮөгӮӨгғҲгӮ„и©ізҙ°гҒӘеҲҶжһҗгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜиӘІйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒжңүж–ҷгғ„гғјгғ«гҒҜй«ҳеәҰгҒӘж©ҹиғҪгӮ„гӮөгғқгғјгғҲгҒҢе……е®ҹгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғҮгғјгӮҝгҒ®ж·ұе ҖгӮҠгӮ„гғҒгғјгғ гҒ§гҒ®е…ұжңүгҒ«е„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒҹгӮҒе°Һе…ҘгҒ«гҒҜдәҲз®—йқўгҒ§гҒ®жӨңиЁҺгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиҮӘзӨҫгҒ®WebгӮөгӮӨгғҲгҒ®иҰҸжЁЎгӮ„еҲҶжһҗзӣ®жЁҷгҒ«еҝңгҒҳгҒҰйҒ©еҲҮгҒӘгғ„гғјгғ«гӮ’йҒёгҒ¶гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҠ№жһңгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢйҒ©еҲҮгҒӘгғҮгғјгӮҝе…ұжңүгҒЁжҙ»з”Ёжі•
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгҒ§еҫ—гҒҹгғҮгғјгӮҝгҒҜгҖҒгғҒгғјгғ еҶ…гҒ§еҠ№жһңзҡ„гҒ«е…ұжңүгҒ—гҖҒе…Ёе“ЎгҒҢжҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢдҪ“еҲ¶гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гғ„гғјгғ«гҒ§гҒҜгҖҒиҰ–иҰҡзҡ„гҒ«гғҮгғјгӮҝгӮ’иЎЁзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғҮгӮ¶гӮӨгғігғҒгғјгғ гӮ„гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гғҒгғјгғ гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе°Ӯй–ҖеӨ–гҒ®гғЎгғігғҗгғјгӮӮзҗҶи§ЈгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҲ©зӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒе®ҡдҫӢдјҡиӯ°гӮ„гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгғҹгғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ§гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®зөҗжһңгӮ’е…ұжңүгҒ—гҖҒеҗ„гғЎгғігғҗгғјгҒ®иҰ–зӮ№гҒӢгӮүж”№е–„гҒ®жҸҗжЎҲгӮ’еӢҹгӮӢгҒЁгӮҲгӮҠеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гғҮгғјгӮҝгӮ’д»–гҒ®WebгӮөгӮӨгғҲгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№и§Јжһҗгғ„гғјгғ«гҒЁгӮӮйҖЈжҗәгҒ—гҖҒгӮҲгӮҠеӨҡи§’зҡ„гҒӘеҲҶжһҗгҒҢиЎҢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжӣҙгҒӘгӮӢж”№е–„гҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮ’еј•гҒҚеҮәгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҹжңӘжқҘгҒ®гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•Ҙ
AIгӮ„ж©ҹжў°еӯҰзҝ’гҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒ§йҖІеҢ–гҒҷгӮӢи§ЈжһҗжҠҖиЎ“
гҖҖиҝ‘е№ҙгҖҒAIгӮ„ж©ҹжў°еӯҰзҝ’гҒ®йҖІеҢ–гҒ«дјҙгҒ„гҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгҒ«гӮӮж–°гҒҹгҒӘеҸҜиғҪжҖ§гҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҠҖиЎ“гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиҶЁеӨ§гҒӘгғҮгғјгӮҝгӮ’еҠ№зҺҮзҡ„гҒӢгҒӨй«ҳеәҰгҒ«и§ЈжһҗгҒ—гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гҒ®ж·ұгҒ„зҗҶи§ЈгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒAIгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гғ„гғјгғ«гҒ§гҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®йқҷзҡ„гҒӘеҲҶжһҗгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒгғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ§гғҲгғ¬гғігғүгӮ’дәҲжё¬гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹй«ҳеәҰгҒӘж©ҹиғҪгҒҢе®ҹзҸҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖеҠ гҒҲгҒҰгҖҒж©ҹжў°еӯҰзҝ’гҒ«гӮҲгӮӢгғ‘гӮҝгғјгғіиӘҚиӯҳжҠҖиЎ“гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгғһгӮҰгӮ№гҒ®еӢ•гҒҚгӮ„гӮҜгғӘгғғгӮҜдҪҚзҪ®гҒӢгӮүгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢжҪңеңЁзҡ„гҒ«жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгӮ’зү№е®ҡгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®UI/UXгӮ’гҒ•гӮүгҒ«жңҖйҒ©еҢ–гҒҷгӮӢж–Ҫзӯ–гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеҫҢгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҠҖиЎ“гҒЁгҒ®йҖЈжҗәгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠй«ҳеәҰгҒӘгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•ҘгӮ’з«ӢжЎҲгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
UXгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®зөұеҗҲгҒ§еүөгӮӢж–°гҒҹгҒӘйЎ§е®ўдҪ“йЁ“
гҖҖгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜUXгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйқһеёёгҒ«е®ҹз”Ёзҡ„гҒӘгғ„гғјгғ«гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—еҲҶжһҗгӮ’зө„гҒҝиҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢWebгӮөгӮӨгғҲдёҠгҒ§дҪ“йЁ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиӘІйЎҢгӮ„жәҖи¶ізӮ№гӮ’еҸҜиҰ–еҢ–гҒ—гҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгӮ’еҹәгҒ«гғҮгӮ¶гӮӨгғіеӨүжӣҙгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§йЎ§е®ўдҪ“йЁ“гӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒӢгӮүеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгғҮгғјгӮҝгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгғҡгғјгӮёгҒ®гҒ©гҒ®йғЁеҲҶгҒҢгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҒ®гҒӢгӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгӮігғігғҶгғігғ„й…ҚзҪ®гӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒзҶҹиӘӯгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЁӘе•ҸиҖ…гҒҢжіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгҒЁйҮҚиҰҒгҒӘгӮігғігғҶгғігғ„гҒҢдёҖиҮҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ§гҒҚгҖҒUIгғҮгӮ¶гӮӨгғіе…ЁдҪ“гҒ®ж•ҙеҗҲжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢи¶іжҺӣгҒӢгӮҠгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒUXгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒЁгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒ®зӣёд№—еҠ№жһңгҒҜгҖҒ競дәүеҠӣгҒ®гҒӮгӮӢWebгӮөгӮӨгғҲж§ӢзҜүгӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гғўгғјгғ«гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ§гҒ®гӮігӮ№гғҲгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ’жңҖеӨ§еҢ–гҒҷгӮӢжҙ»з”Ёжі•
гҖҖгӮ№гғўгғјгғ«гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҷҗгӮүгӮҢгҒҹгғӘгӮҪгғјгӮ№гҒ®дёӯгҒ§WebгӮөгӮӨгғҲгҒ®еҠ№жһңгӮ’жңҖеӨ§йҷҗеј•гҒҚеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҜйҮҚиҰҒгҒӘиӘІйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зӮ№гҒ§гҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜйқһеёёгҒ«иІ»з”ЁеҜҫеҠ№жһңгҒ®й«ҳгҒ„гғ„гғјгғ«гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒз„Ўж–ҷгҒ®гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гғ„гғјгғ«гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒдҪҺгӮігӮ№гғҲгҒ§гғҰгғјгӮ¶гғјиЎҢеӢ•гҒ®еҸҜиҰ–еҢ–гҒЁеҲҶжһҗгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒж–°иҰҸйЎ§е®ўгӮ’гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҹгғ©гғігғҮгӮЈгғігӮ°гғҡгғјгӮёгҒ«гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҖҒгӮҜгғӘгғғгӮҜзҺҮгҒҢдҪҺгҒ„CTAгҒ®дҪҚзҪ®гӮ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз°ЎеҚҳгҒ«гӮігғігғҗгғјгӮёгғ§гғізҺҮеҗ‘дёҠгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҮгғјгӮҝгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹж”№е–„гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘжҠ•иіҮгӮ’гҒ—гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°еҠ№жһңгӮ’ж®өйҡҺзҡ„гҒ«еј•гҒҚдёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгӮ№гғўгғјгғ«гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘWebгӮөгӮӨгғҲж”№е–„гӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҝғеј·гҒ„е‘іж–№гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’и»ёгҒЁгҒ—гҒҹгғҮгғјгӮҝгғүгғӘгғ–гғіж–ҮеҢ–гҒ®ж§ӢзҜү
гҖҖгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгғҮгғјгӮҝгғүгғӘгғ–гғігҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒҜгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷйҮҚиҰҒиҰ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§гҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гҒҜиҰ–иҰҡзҡ„гҖҒзӣҙж„ҹзҡ„гҒ«гғҮгғјгӮҝгҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’дјқгҒҲгӮӢзӮ№гҒ§йқһеёёгҒ«еҪ№з«ӢгҒӨгғ„гғјгғ«гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’и»ёгҒ«гҒ—гҒҹгғҮгғјгӮҝжҙ»з”ЁгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзӨҫеҶ…еӨ–гҒ®гҒӮгӮүгӮҶгӮӢй–ўдҝӮиҖ…гҒҢгғҮгғјгӮҝгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰдёҖиІ«гҒ—гҒҹж–№йҮқгӮ’жү“гҒЎеҮәгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгӮҜгғӘгғғгӮҜгӮ„гӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гҒ®гғ‘гӮҝгғјгғігӮ’е…ұжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жӢ…еҪ“иҖ…гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ„й–ӢзҷәгғҒгғјгғ гӮӮгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®гғӢгғјгӮәгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«иӘҚиӯҳгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ’гғјгғҲгғһгғғгғ—гӮ’дҪҝгҒЈгҒҹеҲҶжһҗгҒ®зөҗжһңгӮ’жҳҺзўәгҒӘKPIгҒ«зөҗгҒід»ҳгҒ‘гҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒ«жҢҜгӮҠиҝ”гӮӢж–ҮеҢ–гӮ’йҶёжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№еҗ‘дёҠгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҮгғјгӮҝгғүгғӘгғ–гғіж–ҮеҢ–гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ競дәүгҒҢжҝҖгҒ—гҒ„з’°еўғгҒ§гҒ®жҢҒз¶ҡзҡ„гҒӘжҲҗй•·гҒ®йҚөгҒЁгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ