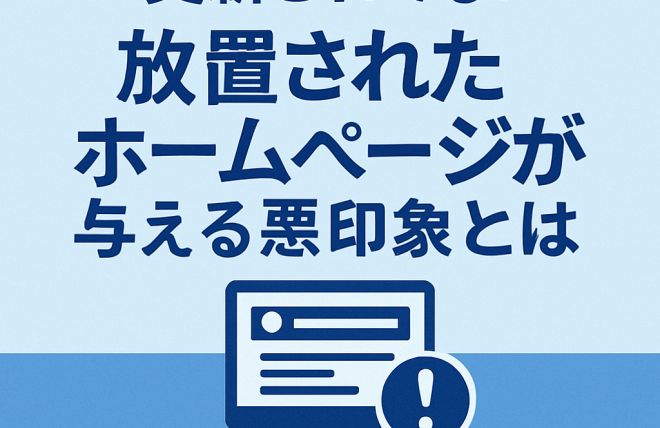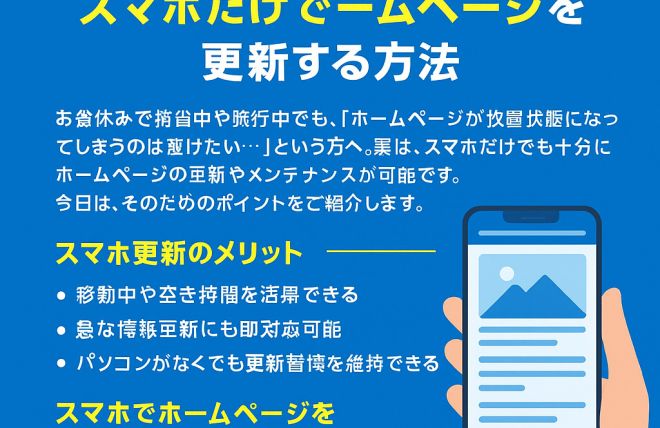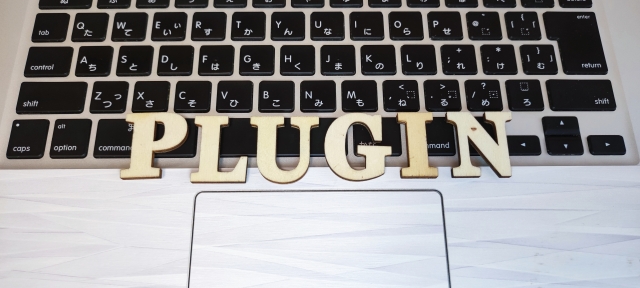еӨҸдј‘гҒҝгҒ®йҡҷгӮ’зӢҷгҒҶж”»ж’ғгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰд»ҠгҒҷгҒҗзўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈй …зӣ®гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲеҪўејҸгҒ§и§ЈиӘ¬гҖӮSSLгҖҒжӣҙж–°гҖҒгғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒӘгҒ©зҹӯжҷӮй–“гҒ§гҒ§гҒҚгӮӢеҜҫзӯ–гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
第1з« : гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒ®еҹәжң¬гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гӮҲгҒҶ
гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘзҗҶз”ұ
гҖҖиҝ‘е№ҙгҖҒгӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгҒ®жүӢеҸЈгҒҢе·§еҰҷеҢ–гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҖӢдәәгӮ„дјҒжҘӯгӮ’е•ҸгӮҸгҒҡгҖҒиӘ°гӮӮгҒҢжЁҷзҡ„гҒ«гҒӘгӮҠгҒҶгӮӢзҠ¶жіҒгҒ§гҒҷгҖӮдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ«гӮҲгӮӢеҖӢдәәжғ…е ұгӮ„ж©ҹеҜҶгғҮгғјгӮҝгҒ®жөҒеҮәгҒҜгҖҒж·ұеҲ»гҒӘиў«е®ігӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’йҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒйЎ§е®ўгғҮгғјгӮҝгӮ’е®ҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜдҝЎй јй–ўдҝӮгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгғӘгӮ№гӮҜгҒӢгӮүжғ…е ұиіҮз”ЈгӮ’е®ҲгӮӢ第дёҖжӯ©гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮҲгҒҸгҒӮгӮӢгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғӘгӮ№гӮҜгҒ®зЁ®йЎһ
гҖҖгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғӘгӮ№гӮҜгҒ«гҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘзЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҖҒгғ•гӮЈгғғгӮ·гғігӮ°и©җж¬әгҖҒгғһгғ«гӮҰгӮ§гӮўж„ҹжҹ“гҖҒгӮҜгғӯгӮ№гӮөгӮӨгғҲгӮ№гӮҜгғӘгғ—гғҶгӮЈгғігӮ°пјҲXSSпјүгҖҒSQLгӮӨгғігӮёгӮ§гӮҜгӮ·гғ§гғігҒӘгҒ©гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҜгҖҒејұгҒ„гғ‘гӮ№гғҜгғјгғүгӮ„гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгҒ®з©ҙгӮ’зӘҒгҒӢгӮҢгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«дҫөе…ҘгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ•гӮЈгғғгӮ·гғігӮ°и©җж¬әгҒҜеҒҪиЈ…гғЎгғјгғ«гӮ„еҒҪгӮөгӮӨгғҲгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҖҒеҖӢдәәжғ…е ұгӮ’зӣ—гҒҝеҸ–гӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡзҷәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒӘгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ„гғ„гғјгғ«гҒ®жҙ»з”ЁгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҲқеҝғиҖ…гҒ«гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғ„гғјгғ«
гҖҖгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®еҲқеҝғиҖ…гҒ«гҒҜгҖҒдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„гғ„гғјгғ«гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰзҸҫзҠ¶гӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒи„ҶејұжҖ§гӮ’зү№е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢгғҚгғғгғҲdeиЁәж–ӯгҖҚгӮ„гҖҢObservatory by MozillaгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®з„Ўж–ҷгғ„гғјгғ«гҒҜгҖҒиҮӘзӨҫгӮөгӮӨгғҲгҒ®и„ҶејұжҖ§гӮ’з°ЎеҚҳгҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еҪ№з«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒҢе°Һе…ҘжёҲгҒҝгҒ®гғ¬гғігӮҝгғ«гӮөгғјгғҗгғјгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гӮӮиүҜгҒ„ж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«Imunify360гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғҗгғјгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈйқўгҒ®иІ жӢ…гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸи»ҪжёӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
第2з« : еҖӢдәәгҒ§з°ЎеҚҳгҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–
гғ‘гӮ№гғҜгғјгғүз®ЎзҗҶгҒ®еҹәжң¬гғ«гғјгғ«
гҖҖе®үе…ЁжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„гғ‘гӮ№гғҜгғјгғүгӮ’иЁӯе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒ®еҹәжң¬гҒ§гҒҷгҖӮз°ЎеҚҳгҒ«жҺЁжё¬гҒ•гӮҢгӮӢгҖҢ123456гҖҚгӮ„гҖҢpasswordгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғ‘гӮ№гғҜгғјгғүгҒҜйҒҝгҒ‘гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒеӨ§ж–Үеӯ—гҒЁе°Ҹж–Үеӯ—гҖҒж•°еӯ—гҖҒиЁҳеҸ·гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹжңҖдҪҺ12ж–Үеӯ—д»ҘдёҠгҒ®еј·еҠӣгҒӘгғ‘гӮ№гғҜгғјгғүгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҗҢгҒҳгғ‘гӮ№гғҜгғјгғүгӮ’иӨҮж•°гҒ®гӮөгӮӨгғҲгҒ§дҪҝгҒ„еӣһгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғӘгӮ№гӮҜгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҗ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ”гҒЁгҒ«з•°гҒӘгӮӢгғ‘гӮ№гғҜгғјгғүгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғ‘гӮ№гғҜгғјгғүз®ЎзҗҶгғ„гғјгғ«гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиӨҮйӣ‘гҒӘгғ‘гӮ№гғҜгғјгғүгӮ’е®үе…ЁгҒ«з®ЎзҗҶгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҖӘгҒ—гҒ„URLгӮ„гғЎгғјгғ«гӮ’иҰӢжҘөгӮҒгӮӢгӮігғ„
гҖҖжҖӘгҒ—гҒ„URLгӮ„гғЎгғјгғ«гӮ’иҰӢжҘөгӮҒгӮӢгӮ№гӮӯгғ«гҒҜгҖҒж—Ҙеёёзҡ„гҒӘгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒиҰӢж…ЈгӮҢгҒӘгҒ„йҖҒдҝЎе…ғгҒӢгӮүгҒ®гғЎгғјгғ«гӮ„гҖҒгӮҜгғӘгғғгӮҜгӮ’дҝғгҒҷгғӘгғігӮҜд»ҳгҒҚгҒ®гғЎгғғгӮ»гғјгӮёгҒ«гҒҜиӯҰжҲ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮURLгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒе…¬ејҸгӮөгӮӨгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгғүгғЎгӮӨгғіеҗҚгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҢhttps://example.com/гҖҚгҒ®гҖҢexample.comгҖҚгҒҢдҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢдјҒжҘӯгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢзўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒзҹӯзё®URLгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгғӘгғігӮҜгҒ«гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡе®үе…ЁжҖ§гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҷгӮӢгғ„гғјгғ«гӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁе®үеҝғгҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғЎгғјгғ«гҒ«ж·»д»ҳгҒ•гӮҢгҒҹгғ•гӮЎгӮӨгғ«гӮ„гғӘгғігӮҜгӮ’дёҚз”Ёж„ҸгҒ«й–ӢгҒҸгҒ®гҒҜйҒҝгҒ‘гҖҒгғӣгғўгӮ°гғ©гғ•ж”»ж’ғгӮ„гӮҝгӮӨгғқгӮ№гӮҜгғҜгғғгғҶгӮЈгғігӮ°пјҲдјјгҒҹеҗҚеүҚгҒ®URLпјүгҒ«гӮӮжіЁж„ҸгҒҷгӮӢзҝ’ж…ЈгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгӮ„OSгҒ®е®ҡжңҹзҡ„гҒӘгӮўгғғгғ—гғҮгғјгғҲ
гҖҖдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгӮ„OSгӮ’еёёгҒ«жңҖж–°гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«дҝқгҒӨгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮөгӮӨгғҗгғјгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒ®дёӯж ёгӮ’гҒӘгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҸӨгҒ„гғҗгғјгӮёгғ§гғігҒ®гҒҫгҒҫж”ҫзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒж—ўзҹҘгҒ®и„ҶејұжҖ§гӮ’жӮӘз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢгҒҹгӮҒжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮдёҖйғЁгҒ®гӮўгғғгғ—гғҮгғјгғҲгҒ«гҒҜгҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈдёҠгҒ®ејұзӮ№гӮ’дҝ®жӯЈгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘгғ‘гғғгғҒгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒжӣҙж–°йҖҡзҹҘгӮ’иҰӢиҗҪгҒЁгҒ•гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒзү№гҒ«дјҒжҘӯгӮөгӮӨгғҲгӮ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’йҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒWebгӮөгғјгғҗгғјгӮ„з®ЎзҗҶгғ„гғјгғ«гӮӮе®ҡжңҹзҡ„гҒ«гӮўгғғгғ—гғҮгғјгғҲгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒиҝҪеҠ гҒ§гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгғӘгӮ№гӮҜгӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгӮӢеҠӘеҠӣгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
第3з« : гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёйҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғҒгӮ§гғғгӮҜ
гӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲгҒ®и„ҶејұжҖ§иЁәж–ӯгғ„гғјгғ«гҒ®жҙ»з”Ё
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒи„ҶејұжҖ§иЁәж–ӯгғ„гғјгғ«гҒ®жҙ»з”ЁгҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғ„гғјгғ«гҒҜгҖҒгӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲгҒҢжҢҒгҒӨжҪңеңЁзҡ„гҒӘгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғӘгӮ№гӮҜгӮ’иҮӘеӢ•гҒ§зҷәиҰӢгҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘеҜҫзӯ–гӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢжүӢеҠ©гҒ‘гӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢгғҚгғғгғҲdeиЁәж–ӯгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®з„Ўж–ҷгғ„гғјгғ«гӮ’дҪҝгҒҲгҒ°гҖҒиҮӘзӨҫгӮөгӮӨгғҲгҒ®и„ҶејұжҖ§гӮ’жүӢи»ҪгҒ«зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«дёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ„жғ…е ұжөҒеҮәгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒӘиЁәж–ӯгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғ»гғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒжјҸгӮҢгҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒЁиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
HTTPSеҢ–гҒҢгӮӮгҒҹгӮүгҒҷе®үе…ЁжҖ§еҗ‘дёҠ
гҖҖгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёйҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒHTTPSеҢ–гҒҜеҹәжң¬дёӯгҒ®еҹәжң¬гҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүйқһеёёгҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒӘгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒ§гҒҷгҖӮHTTPSеҢ–гҒҜгҖҒSSLгӮөгғјгғҗгғјиЁјжҳҺжӣёгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰйҖҡдҝЎгӮ’жҡ—еҸ·еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ第дёүиҖ…гҒ«гӮҲгӮӢгғҮгғјгӮҝгҒ®зӣ—гҒҝиҰӢгӮ„ж”№гҒ–гӮ“гӮ’йҳІгҒҺгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒйЎ§е®ўгҒӢгӮүгҒ®дҝЎй јж„ҹгҒ®еҗ‘дёҠгӮ„гҖҒжӨңзҙўгӮЁгғігӮёгғігҒ§гҒ®и©•дҫЎгӮўгғғгғ—гҒ«гӮӮгҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеҖӢдәәжғ…е ұгӮ„гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжғ…е ұгӮ’жүұгҒҶгӮөгӮӨгғҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеҝ…й ҲгҒ®еҜҫзӯ–гҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгӮөгӮӨгғҗгғјгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈвҖ•еҜҫзӯ–гғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲгҒ«еҝ…гҒҡHTTPSеҢ–гӮ’еҗ«гӮҒгҖҒдёҮе…ЁгҒ®жә–еӮҷгӮ’ж•ҙгҒҲгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігҒ®е°Һе…Ҙж–№жі•
гҖҖCMSпјҲгӮігғігғҶгғігғ„з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ пјүгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігҒ®е°Һе…ҘгҒҢеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгӮ’еј·еҢ–гҒ—гҖҒдёҚжӯЈгғӯгӮ°гӮӨгғігӮ„ж”»ж’ғгҒӢгӮүдҝқиӯ·гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒWordPressгҒ§гҒҜгҖҢWordfenceгҖҚгӮ„гҖҢAll In One WP SecurityгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®гғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігҒҢгӮҲгҒҸдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғ„гғјгғ«гҒҜи„ҶејұжҖ§гҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ„дёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ®и©ҰгҒҝгӮ’йҳІгҒҗгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒйҖҡзҹҘж©ҹиғҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ§иӯҰе‘ҠгӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮе°Һе…ҘгҒ®йҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒҢе°Һе…ҘжёҲгҒҝгҒ®гғ¬гғігӮҝгғ«гӮөгғјгғҗгғјгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ•гӮүгҒ«е®үеҝғгҒ§гҒҷгҖӮ
第4з« : дёҮгҒҢдёҖгҒ«еӮҷгҒҲгӮӢгғҲгғ©гғ–гғ«еҜҫзӯ–
иў«е®ігӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгӮӢгғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—
гҖҖгӮөгӮӨгғҗгғјгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒӘгғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒҜиў«е®ігӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮдёҚжӯЈгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ„гғһгғ«гӮҰгӮ§гӮўж”»ж’ғгҒӘгҒ©гҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гӮӮгҖҒзӣҙиҝ‘гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гғҮгғјгӮҝгӮ’еҫ©е…ғгҒ§гҒҚгӮӢгғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘжҗҚеӨұгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҢгғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒ®жңүз„ЎгҖҚгҒҜйҮҚиҰҒгҒӘй …зӣ®гҒЁгҒ—гҒҰжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гӮ’з°ЎеҚҳгҒ«з®ЎзҗҶгҒ§гҒҚгӮӢгӮҜгғ©гӮҰгғүгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгӮөгғјгғҗгғјгҒ®иҮӘеӢ•гғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—ж©ҹиғҪгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдёҮгҒҢдёҖгҒ®дәӢж…ӢгҒ«гӮӮиҝ…йҖҹгҒ«еҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢдҪ“еҲ¶гӮ’ж•ҙгҒҲгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҒ®еҲқеӢ•еҜҫеҝң
гҖҖгӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҖҒеҲқеӢ•еҜҫеҝңгҒҢиў«е®іжӢЎеӨ§гӮ’йҳІгҒҗйҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒиў«е®ігӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҹжҷӮзӮ№гҒ§зӣҙгҒЎгҒ«еҜҫиұЎгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜжҺҘз¶ҡгӮ’йҒ®ж–ӯгҒ—гҖҒдҫөе…ҘзөҢи·ҜгӮ’зү№е®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гғӯгӮ°иӘҝжҹ»гӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҖҒжңҖж–°гҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғ»гғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«йҒ©еҲҮгҒӘжүӢй ҶгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒиў«е®ігҒҢеӨ§гҒҚгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҜе°Ӯй–Җж©ҹй–ўгҒёгҒ®зӣёи«ҮгӮ’иҰ–йҮҺгҒ«е…ҘгӮҢгҒӨгҒӨгҖҒдәӢеүҚгҒ«гғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰиҝ…йҖҹгҒ«еҫ©е…ғгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәӢж…ӢгҒ®еҸҺжқҹгӮ’ж—©гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
зӣёи«Үе…ҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈе°Ӯй–Җж©ҹй–ў
гҖҖдёҮгҒҢдёҖгӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈе°Ӯй–Җж©ҹй–ўгҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҜҫзӯ–гҒ®дёҖз’°гҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәJPCERTгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮ·гғ§гғігӮ»гғігӮҝгғјгӮ„IPAпјҲжғ…е ұеҮҰзҗҶжҺЁйҖІж©ҹж§ӢпјүгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ§гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиў«е®іе ұе‘ҠгӮ„зӣёи«ҮзӘ“еҸЈгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«дәӢдҫӢгҒ«еҹәгҒҘгҒҸе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹж”ҜжҸҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈиЁәж–ӯгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„гғҒгӮ§гғғгӮҜгғ„гғјгғ«гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢе°Ӯй–Җж©ҹй–ўгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёйҒӢе–¶иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгӮ’жҢҒгҒӨж©ҹй–ўгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒҜиў«е®іжӢЎеӨ§гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҶҚзҷәйҳІжӯўзӯ–гҒ®зӯ–е®ҡгҒ«гӮӮеҜ„дёҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ