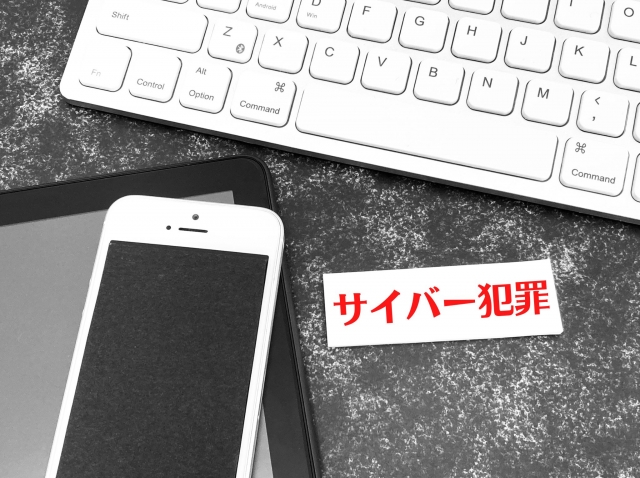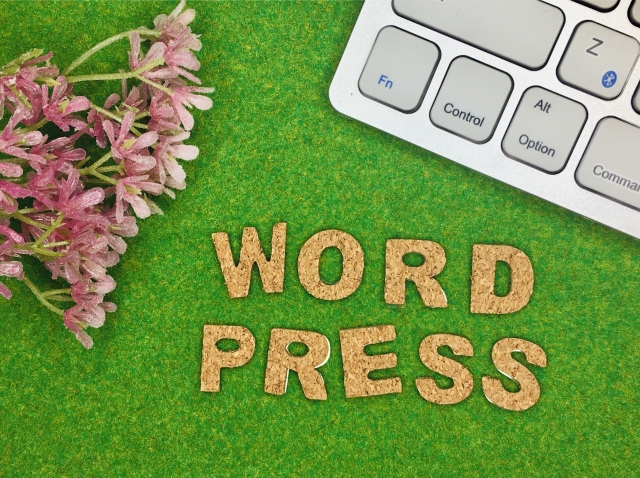InstagramгҖҒTikTokгҖҒXпјҲж—§TwitterпјүгҖҒYouTubeвҖҰгҖӮгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҜж—ҘгҖ…гҒ®SNSгҒ®дёӯгҒ§гҖҢеҒ¶з„¶еҮәдјҡгҒҶгҖҚе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«еҝғгӮ’еӢ•гҒӢгҒ•гӮҢгҖҒиҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ«WebгӮөгӮӨгғҲгҒёгҒЁиЁӘгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒЁгҒҜпјҹеҹәжң¬жҰӮеҝөгҒЁгҒқгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§
иіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒ®жҰӮиҰҒ
гҖҖиіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒЁгҒҜгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’дҪ“зі»зҡ„гҒ«зӨәгҒ—гҒҹгғ•гғ¬гғјгғ гғҜгғјгӮҜгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жғ…е ұгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҖҒй–ўеҝғгӮ’й«ҳгӮҒгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«иіјиІ·иЎҢеӢ•гҒ«иҮігӮӢгҒ®гҒӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҹәзӣӨгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгӮ„SNSгҒ®жҷ®еҸҠгҒ«дјҙгҒ„гҖҒиіјиІ·иЎҢеӢ•гҒҢгғҮгӮёгӮҝгғ«гғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ дёҠгҒ§е®ҢзөҗгҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮеў—гҒҲгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ„WebгӮөгӮӨгғҲгҒ®жҲҰз•ҘиЁӯиЁҲгҒ§гӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒ«е°ҺгҒҸйҮҚиҰҒгҒӘйҚөгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҷӮд»ЈгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еӨүеҢ–гҒҷгӮӢж¶ҲиІ»иҖ…еҝғзҗҶгҒЁиЎҢеӢ•
гҖҖж¶ҲиІ»иҖ…еҝғзҗҶгӮ„иіјиІ·иЎҢеӢ•гҒҜгҖҒжҷӮд»ЈгӮ„гғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒ®йҖІеҢ–гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеҫ“жқҘгҒҜгғҶгғ¬гғ“еәғе‘ҠгӮ„йӣ‘иӘҢгҒӘгҒ©гҒ®дёҖж–№зҡ„гҒӘжғ…е ұжҸҗдҫӣгҒ«й јгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒSNSгҒ®зҷәеұ•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒд»ҠгҒ§гҒҜеҸЈгӮігғҹгӮ„гғ¬гғ“гғҘгғјгҖҒгғҸгғғгӮ·гғҘгӮҝгӮ°жӨңзҙўгҒ§з°ЎеҚҳгҒ«жғ…е ұгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢжҷӮд»ЈгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«Zдё–д»ЈгӮ„гғҹгғ¬гғӢгӮўгғ«дё–д»ЈгҒҜгҖҒSNSгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҜ”ијғжӨңиЁҺгҒ—гҖҒд»–гҒ®гғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®ж„ҸиҰӢгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨүеҢ–гҒҜгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°ж–Ҫзӯ–гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮз„ЎиҰ–гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„иҰҒзҙ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиіјиІ·гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®еҪ№еүІ
гҖҖиіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•ҘгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢжӨңзҙўгӮЁгғігӮёгғігӮ„SNSгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«иіјиІ·гҒ«иҮігӮӢзөҢи·ҜгӮ’жҳҺзўәгҒ«жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғһгғјгӮұгӮҝгғјгҒҜжңҖйҒ©гҒӘгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§жғ…е ұгӮ„еәғе‘ҠгӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«SNSгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢиіјиІ·иЎҢеӢ•гҒҢеў—гҒҲгҒҹзҸҫд»ЈгҒ§гҒҜгҖҒSNSгҒЁWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®йҖЈжҗәгӮ’еј·еҢ–гҒ—гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢжғ…е ұгӮ’еҠ№зҺҮзҡ„гҒ«еұҠгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒйЎ§е®ўдҪ“йЁ“гӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгҖҒй•·жңҹзҡ„гҒӘгғ–гғ©гғігғүдҫЎеҖӨгҒ®еҗ‘дёҠгӮ’зӢҷгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
дјқзөұзҡ„гҒӘиіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«пјҡAIDMAгҒӢгӮүAISASгҒёгҒ®йҖІеҢ–
AIDMAгғўгғҮгғ«пјҡиіјиІ·иЎҢеӢ•гҒ®еҹәжң¬гғ•гғ¬гғјгғ гғҜгғјгӮҜ
гҖҖAIDMAпјҲгӮўгӮӨгғүгғһпјүгҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҖҢAttentionпјҲжіЁж„ҸпјүгҖҚгҖҒгҖҢInterestпјҲй–ўеҝғпјүгҖҚгҖҒгҖҢDesireпјҲж¬ІжұӮпјүгҖҚгҖҒгҖҢMemoryпјҲиЁҳжҶ¶пјүгҖҚгҖҒгҖҢActionпјҲиЎҢеӢ•пјүгҖҚгҒ®5гҒӨгҒ®гӮ№гғҶгғғгғ—гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢгҒӮгӮӢе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«еҮәдјҡгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгҒ«иҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҖҒиіје…ҘгӮ’гҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жөҒгӮҢгӮ’гғ•гғ¬гғјгғ гғҜгғјгӮҜгҒЁгҒ—гҒҰзӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгғҶгғ¬гғ“гҖҒж–°иҒһгҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒӘгҒ©гҒ®гғһгӮ№гғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹдёҖж–№зҡ„гҒӘжғ…е ұзҷәдҝЎгҒҢдё»жөҒгҒ гҒЈгҒҹжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒAIDMAгҒҢж¶ҲиІ»иҖ…еҝғзҗҶгӮ„иіјиІ·гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®зҗҶи§ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйқһеёёгҒ«жңүеҠ№гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгӮ„SNSгҒ®жҷ®еҸҠгҒ«дјҙгҒ„гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒЁгҒ®еҸҢж–№еҗ‘гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢзҸҫеңЁгҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҠ№жһңгҒҢйҷҗе®ҡзҡ„гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиӘІйЎҢгӮӮжө®гҒҚеҪ«гӮҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
AISASгғўгғҮгғ«гҒ®зҷ»е ҙгҒЁгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒ®еҪұйҹҝ
гҖҖгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒ®жҷ®еҸҠгҒ«дјҙгҒ„гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®жғ…е ұеҸҺйӣҶжүӢж®өгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жөҒгӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰзҷ»е ҙгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢAISASпјҲгӮўгӮӨгӮөгӮ№пјүгғўгғҮгғ«гҒ§гҒҷгҖӮAISASгҒҜгҖҢAttentionпјҲжіЁж„ҸпјүгҖҚгҖҒгҖҢInterestпјҲй–ўеҝғпјүгҖҚгҖҒгҖҢSearchпјҲжӨңзҙўпјүгҖҚгҖҒгҖҢActionпјҲиЎҢеӢ•пјүгҖҚгҖҒгҖҢShareпјҲе…ұжңүпјүгҖҚгҒ®5гҒӨгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒеҫ“жқҘгҒ®AIDMAгғўгғҮгғ«гҒ«гҖҢжӨңзҙўгҖҚгҒЁгҖҢе…ұжңүгҖҚгҒҢиҝҪеҠ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖзү№гҒ«гҖҢжӨңзҙўпјҲSearchпјүгҖҚгҒ®гғ•гӮ§гғјгӮәгҒҜгҖҒе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«иҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢWebгӮөгӮӨгғҲгӮ„еҸЈгӮігғҹгӮ’жҺўгҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘжғ…е ұгӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘж®өйҡҺгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢе…ұжңүпјҲShareпјүгҖҚгҒ®гғ•гӮ§гғјгӮәгҒ§гҒҜгҖҒSNSгӮ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®жғ…е ұгӮ’д»–иҖ…гҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж–°гҒҹгҒӘж¶ҲиІ»иҖ…гӮ’е·»гҒҚиҫјгӮҖеҠ№жһңгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдјҒжҘӯгҒ®гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҙ»еӢ•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®еҪ№еүІгӮ„SNSгҒ®еҪұйҹҝеҠӣгҒҢгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
AISASгҒҢеҲҮгӮҠй–ӢгҒ„гҒҹгғҮгӮёгӮҝгғ«гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®ж–°жҷӮд»Ј
гҖҖAISASгғўгғҮгғ«гҒ®е°Һе…ҘгҒҜгҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж–°гҒҹгҒӘжҷӮд»ЈгӮ’еҲҮгӮҠй–ӢгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҫ“жқҘгҒ®дёҖж–№еҗ‘зҡ„гҒӘеәғе‘ҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…иҮӘиә«гҒҢиғҪеӢ•зҡ„гҒ«жғ…е ұгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒ•гӮүгҒ«жӢЎж•ЈгҒҷгӮӢгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖзү№гҒ«InstagramгӮ„YouTubeгҒӘгҒ©гҒ®SNSгҒҜгҖҒиҰ–иҰҡзҡ„гҒӘжғ…е ұгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢй–ўеҝғпјҲInterestпјүгҖҚгҒ®е–ҡиө·гҒӢгӮүгҖҢе…ұжңүпјҲShareпјүгҖҚгҒ®дҝғйҖІгҒҫгҒ§гҖҒдёҖйҖЈгҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’еҠ йҖҹгҒ•гҒӣгӮӢеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒZдё–д»ЈгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒ—гҒҹиӢҘгҒ„дё–д»ЈгҒ§гҒҜгҖҒгғҸгғғгӮ·гғҘгӮҝгӮ°жӨңзҙўгӮ„еҸЈгӮігғҹгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹжғ…е ұеҸҺйӣҶгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҪјгӮүгӮ’гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒSNSгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹжҲҰз•ҘгӮ’иҖғгҒҲгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖAISASгғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгӮ„SNSгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гҒ®еӨүеҢ–гӮ’зҡ„зўәгҒ«жҚүгҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жӢ…еҪ“иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„гғ•гғ¬гғјгғ гғҜгғјгӮҜгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮSNSгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢиіјиІ·иЎҢеӢ•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгҒ®еҪ№еүІгӮӮеј•гҒҚз¶ҡгҒҚйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжғ…е ұжҸҗдҫӣгҒ®гғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жҙ»з”ЁгҒҢйҚөгӮ’жҸЎгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
SNSжҷӮд»ЈгҒ®ж–°иіјиІ·гғўгғҮгғ«пјҡSIPSгҒЁULSSAS
SIPSгғўгғҮгғ«пјҡеҸЈгӮігғҹгҒЁе…ұж„ҹгҒҢз”ҹгӮҖиіјиІ·иЎҢеӢ•
гҖҖSIPSгғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒSNSгҒ®жҷ®еҸҠгҒ«дјҙгҒЈгҒҰзҷ»е ҙгҒ—гҒҹиіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒ§гҖҒSympathizeпјҲе…ұж„ҹгҒҷгӮӢпјүгҖҒIdentifyпјҲзўәиӘҚгҒҷгӮӢпјүгҖҒParticipateпјҲеҸӮеҠ гҒҷгӮӢпјүгҖҒShare & SpreadпјҲе…ұжңүгҒ—гҒҰеәғгӮҒгӮӢпјүгҒ®4ж®өйҡҺгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гҒ§гҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®еәғе‘Ҡдё»дҪ“гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…иҮӘиә«гҒҢдёӯеҝғгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰжғ…е ұгӮ’е…ұжңүгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҪұйҹҝгӮ’жӢЎеӨ§гҒ•гҒӣгӮӢд»•зө„гҒҝгҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖSNSеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®зҙ„80%гҒҢиіјиІ·иЎҢеӢ•гҒ«SNSгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢзҸҫд»ЈгҒ§гҒҜгҖҒSIPSгғўгғҮгғ«гҒҜзү№гҒ«жңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒInstagramгҒ§зӣ®гҒ«гҒ—гҒҹе•Ҷе“ҒгҒ®еҸЈгӮігғҹгӮ„гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§иҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«иіје…ҘгҒ«иҮігӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡж•°иҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғҸгғғгӮ·гғҘгӮҝгӮ°гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒиҮӘеҲҶгҒҢиіје…ҘгҒ—гҒҹе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’зҷәдҝЎгҒҷгӮӢиЎҢзӮәгӮӮгҖҒд»–гҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®е…ұж„ҹгӮ’е‘јгҒійҖЈйҺ–зҡ„гҒӘиіјиІ·иЎҢеӢ•гӮ’з”ҹгӮҖиҰҒеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«SIPSгғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’гҒҹгҒ еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдё»дҪ“зҡ„гҒ«жғ…е ұзҷәдҝЎгӮ„е…ұжңүгҒ«й–ўдёҺгҒҷгӮӢзӮ№гҒ§еӨ§гҒҚгҒӘеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒSNSгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•ҘгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж¬ гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„иҰ–зӮ№гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ULSSASгғўгғҮгғ«пјҡSNSдё»е°ҺгҒ®иіјиІ·гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒЁгҒҜ
гҖҖULSSASгғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒSNSдё»е°ҺгҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гӮ’зү№еҫҙд»ҳгҒ‘гӮӢжңҖиҝ‘гҒ®гғ•гғ¬гғјгғ гғҜгғјгӮҜгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғўгғҮгғ«гҒ§гҒҜUncoverпјҲзҷәиҰӢпјүгҖҒLikeпјҲе…ұж„ҹгҒҷгӮӢпјүгҖҒShareпјҲе…ұжңүгҒҷгӮӢпјүгҖҒSearchпјҲжӨңзҙўгҒҷгӮӢпјүгҖҒActionпјҲиЎҢеӢ•гҒҷгӮӢпјүгҖҒSpreadпјҲеәғгӮҒгӮӢпјүгҒ®6ж®өйҡҺгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиіјиІ·гҒҢйҖІгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«SNSгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢжңҖеҲқгҒ«е•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’гҖҢзҷәиҰӢгҖҚгҒҷгӮӢгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз¶ҡгҒ„гҒҰгҖҢе…ұж„ҹгҖҚгӮ„гҖҢе…ұжңүгҖҚгҒ«иҮігӮӢжөҒгӮҢгҒ§еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖULSSASгғўгғҮгғ«гҒ®еј·гҒҝгҒҜгҖҒгҒқгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢSNSзү№жңүгҒ®зһ¬жҷӮжҖ§гҒЁгғҗгӮӨгғ©гғ«жҖ§гҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒInstagramгӮ„XпјҲж—§TwitterпјүгҒ§и©ұйЎҢгҒ®е•Ҷе“ҒгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҸӢдәәгӮ„гғ•гӮ©гғӯгғҜгғјгҒЁе…ұжңүгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҖҒгҒ•гӮүгҒ«и©ізҙ°гҒӘжғ…е ұгӮ’WebгӮөгӮӨгғҲгҒӘгҒ©гҒ§жӨңзҙўгҒ—гҖҒиіје…ҘгҒ«иҮігӮӢжөҒгӮҢгҒҜйқһеёёгҒ«дёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮзҸҫеңЁгҒ§гҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒ®е…¬ејҸгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ„е•Ҷе“ҒгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжғ…е ұгҒ®е……е®ҹеәҰгҒҢиіјиІ·гҒ®жңҖзөӮжұәе®ҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒ21дё–зҙҖгҒ®SNSгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҜгҖҒеҖӢдәәгҒ®еҸЈгӮігғҹгӮ’дёҖзЁ®гҒ®гҖҢдҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢгғЎгғҮгӮЈгӮўгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дјҒжҘӯгҒҢSIPSеҗҢж§ҳгҒ«ULSSASгғўгғҮгғ«гӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒҹгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•ҘгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ULSSASгҒҢгӮӮгҒҹгӮүгҒҷеёӮе ҙеӨүеҢ–гҒЁгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•Ҙ
гҖҖULSSASгғўгғҮгғ«гҒҢжҷ®еҸҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзҸҫеңЁгҒ®гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•ҘгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘеӨүеҢ–гӮ’йҒӮгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдјҒжҘӯгҒҢзӣҙжҺҘж¶ҲиІ»иҖ…гҒ«гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…еҗҢеЈ«гҒ®жғ…е ұе…ұжңүгӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠиҮӘ然гҒ§еҪұйҹҝеҠӣгҒ®еј·гҒ„иЁҙжұӮгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҲҰз•ҘгҒҜзү№гҒ«Zдё–д»ЈгҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҠ№жһңгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҖҒSNSгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®иЎҢеӢ•гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒе•Ҷе“ҒгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ„гғ—гғӯгғўгғјгӮ·гғ§гғігҒ®еңЁгӮҠж–№гҒ«гӮӮеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢSNSгҒ§зҷәдҝЎгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҢгӮ·гӮ§гӮўгҒ—гҒҹгҒҸгҒӘгӮӢгҖҚгӮігғігғҶгғігғ„гӮ„е•Ҷе“ҒгҒ®й–ӢзҷәгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒWebгӮөгӮӨгғҲгӮ„е…¬ејҸгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®еҪ№еүІгӮӮйҮҚиҰҒжҖ§гӮ’еў—гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒSNSгҒ§еҫ—гҒҹй–ўеҝғгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«жғ…е ұеҸҺйӣҶгӮ’иЎҢгҒҶж¶ҲиІ»иҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒжҳҺзўәгҒӢгҒӨи©ізҙ°гҒӘжғ…е ұгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢе ҙгҒЁгҒ—гҒҰйҖІеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖULSSASгғўгғҮгғ«гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•ҘгҒ®жҲҗеҠҹдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгӮӨгғігғ•гғ«гӮЁгғігӮөгғјгӮ„гғҰгғјгӮ¶гғјдё»е°ҺгҒ®гғ—гғӯгғўгғјгӮ·гғ§гғігӮӯгғЈгғігғҡгғјгғігҖҒгҒқгҒ—гҒҰдјҒжҘӯгҒЁж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢеҸҢж–№еҗ‘гҒ§з№ӢгҒҢгӮӢж–Ҫзӯ–гҒӘгҒ©гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдјҒжҘӯгҒҜгӮҲгӮҠеӨҡдё–д»ЈгҒ«гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒе…ұж„ҹгӮ„дҝЎй јгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹй•·жңҹзҡ„гҒӘгғ–гғ©гғігғүдҫЎеҖӨгҒ®еҗ‘дёҠгӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒ®жңӘжқҘпјҡж–°гҒҹгҒӘеҸҜиғҪжҖ§гҒЁжҢ‘жҲҰ
AIгҒЁгғ“гғғгӮ°гғҮгғјгӮҝгҒҢзӨәгҒҷеҖӢеҲҘеҢ–гҒҷгӮӢиіјиІ·гғ—гғӯгӮ»гӮ№
гҖҖAIгҒЁгғ“гғғгӮ°гғҮгғјгӮҝгҒҢйҖІеҢ–гҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢзҸҫд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гҒҜгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷеҖӢеҲҘеҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгғ‘гӮҝгғјгғіеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢд»®е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгғ“гғғгӮ°гғҮгғјгӮҝгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®и¶Је‘іе—ңеҘҪгӮ„иіјиІ·еұҘжӯҙгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜSNSгҒ§гҒ®зҷәиЁҖгӮ„иЎҢеӢ•гҒҢи©ізҙ°гҒ«еҲҶжһҗгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…дёҖдәәгҒІгҒЁгӮҠгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°ж–Ҫзӯ–гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҠ№жһңгҒҢж јж®өгҒ«еҗ‘дёҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒзү№е®ҡгҒ®дё–д»ЈгӮ„гғ©гӮӨгғ•гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹе•Ҷе“ҒгӮ’жҸҗжЎҲгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒAIгҒҢSNSгҒ®еҲ©з”ЁеұҘжӯҙгӮ„WebгӮөгӮӨгғҲгҒ®й–ІиҰ§еұҘжӯҙгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҢжңӣгӮҖгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§йҒ©еҲҮгҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒAIгҒЁгғ“гғғгӮ°гғҮгғјгӮҝгҒҜгҖҒиіјиІ·иЎҢеӢ•гӮ’гӮҲгӮҠзІҫз·»еҢ–гҒ—гҖҒеҖӢеҲҘеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°е…ЁиҲ¬гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…дҪ“йЁ“иҮӘдҪ“гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸеӨүйқ©гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒҢиіјиІ·иЎҢеӢ•гҒ«дёҺгҒҲгӮӢгҒ•гӮүгҒӘгӮӢеҪұйҹҝ
гҖҖгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒ®йҖІеҢ–гҒҜгҖҒиіјиІ·иЎҢеӢ•гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’йқ©ж–°гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒSNSгӮ„WebгӮөгӮӨгғҲгӮ’йҖҡгҒҳгҒҹжғ…е ұеҸҺйӣҶгҒҢеҠ йҖҹгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®иЎҢеӢ•гғ‘гӮҝгғјгғігӮ’еӨүеҢ–гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮSNSгҒ§гҒ®гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒжҠ•зЁҝгӮ„гӮӨгғігғ•гғ«гӮЁгғігӮөгғјгҒ®гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҖҒе•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ®еҲқжҺҘзӮ№гҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гӮӢйҮҚиҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…гҒҜгҖҒSNSгҒ§иҲҲе‘ігӮ’жҢҒгҒЈгҒҹе•Ҷе“ҒгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫECгӮөгӮӨгғҲгӮ„гғ–гғ©гғігғүе…¬ејҸгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§иіје…ҘгҒҷгӮӢиЎҢеӢ•гӮ’еҸ–гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғҒгғЈгғғгғҲгғңгғғгғҲгӮ„гғ‘гғјгӮҪгғҠгғ©гӮӨгӮәгҒ•гӮҢгҒҹеәғе‘ҠгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҜгӮҲгӮҠзҹӯгҒ„жҷӮй–“гҒ§ж„ҸжҖқжұәе®ҡгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒSNSгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢиіјиІ·иЎҢеӢ•гҒҢеҫ“жқҘд»ҘдёҠгҒ«йҖҹеәҰгӮ’еў—гҒҷеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йҖІеұ•гҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒҜгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҙ»еӢ•гҒ®дёӯгҒ§гӮӮйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷиҰҒзҙ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҠеҫҢгҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«й–ӢзҷәгҒёгҒ®жңҹеҫ…
гҖҖжңӘжқҘгҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒ«гҒҜгҖҒгҒ•гӮүгҒӘгӮӢжҹ”и»ҹжҖ§гҒЁйҒ©еҝңеҠӣгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®дҫЎеҖӨиҰігӮ„зӨҫдјҡзҠ¶жіҒгҒҜеёёгҒ«еӨүеҢ–гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒSNSгӮ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғҮгӮёгӮҝгғ«гғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒ®еҪ№еүІгӮӮйҖІеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«Zдё–д»ЈгҒҜSNSгӮ’дё»гҒӘжғ…е ұеҸҺйӣҶгҒ®е ҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҒ®й–ӢзҷәгҒҢжҖҘеӢҷгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖж ӘејҸдјҡзӨҫTOKYO GATEгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘECгӮ„гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®е°Ӯй–Җ家йӣҶеӣЈгҒҢгҖҒжңҖж–°гҒ®гғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒЁгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•ҘгӮ’й§ҶдҪҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж–°гҒҹгҒӘиіјиІ·иЎҢеӢ•гғўгғҮгғ«гҒ®жҸҗжЎҲгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®иіјиІ·иЎҢеӢ•гӮ’гҒ•гӮүгҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒ«еҲҶжһҗгҒ—гҖҒдјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮжңҖйҒ©гҒӘгғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢжңӘжқҘгҒ®иіјиІ·гғўгғҮгғ«вҖ•вҖ•гҒқгӮҢгҒҜAIгӮ„гғ“гғғгӮ°гғҮгғјгӮҝгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…дёҖдәәгҒІгҒЁгӮҠгҒ®е…ұж„ҹгӮ„дҝЎй јгҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ